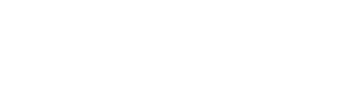Contents
就活における「作文」とは何か
就活では「作文」や「小論文」を提出する、またはその筆記試験が行われます。エントリーシートの各質問に対する答えも、文章量はそれほど多くいありませんが「作文」です。
更にエントリーシート提出と同タイミングで企業が求めるテーマについての作文を提出する、あるいは筆記試験の1分野として「作文」を提出するケースもあります。
マスコミ系の企業では、上記に加え「小論文」の筆記試験があり、一般企業より難易度の高いテーマが設定されます。
つまり、エントリーシートの各質問に関する答えを「作文」と考えれば、就活で「作文」を回避することはできません。
選考を通過していくために、「文章力」、「作文力」は必須のチカラなのです。
就活「作文」の読者を理解しよう
就活における「作文」の読者は企業の人事部、採用担当者、役員ということになります。エントリーシートでの提出はもとより、筆記試験で「作文」や「小論文」が行われる場合は、殆どの場合二次・三次面接の前になるため、メインの読者は人事担当・部門の採用担当者です。
そこを通過すると、エントリーシートと筆記試験、面接評価のスコアと共に、作文が資料として役員面接や最終面接への出席者に「資料」として配布されると考えておいてください。
就活の「作文」では何をチェックされるのか
企業は志望者の「作文」により、「文章のコミュニケーション能力」と「企業の価値観や求める人材像とのマッチング」をチェック、評価します。
まず志望者の「作文」によって「文章のコミュニケーション能力」を以下のポイントでチェックします
- 設問やテーマを正しく理解できているか
- 自分の意見、論点を整理できているか
- 説得力のある文章の構成、内容があるか
- 人に伝えるための工夫や努力(読みやすさや、丁寧さ)があるか
- 日本語の文章としての正しさ
次に、内容では「企業の価値観や求める人材像とのマッチング」をチェックすることになります。
例えば「あなたが学生時代に、最も主体的に取り組んだこと」というテーマをエントリーシートや筆記試験で設定した場合、企業側は「あなたが、主体性というものをどのように捉え、どんな活動を行っていたのか」を知ることによって、自社とのマッチングをチェックするのです。
主体的に取り組んだものがスポーツであった場合、チームスポーツなのか個人なのか、部での役割や、具体的な活動の中身によっても「主体性」は違った表現になるでしょう。
その違いを通じて「あなたにとっての主体性」と「企業が求める主体性」のマッチング度合いをチェックするのです。
もちろん、その設問やその回答である文章のみで、「企業の価値観や求める人材像とのマッチング」を見ている訳ではありません。しかしESでの様々な回答が書類選考である以上、「あなた」を伝える「文章力」、「作文力」は就活に必須の能力なのです。
就活「作文」の類型を理解しておこう
「企業の価値観や求める人材像とのマッチング」をチェック、評価するための作文のテーマの大枠は以下のように分類できます。就活で良く出る「作文」のテーマと考えてください。
- あなたの過去についてのテーマ
- あなたの現在についてのテーマ
- あなたの未来についてのテーマ
一つずつ解説していきます。
あなたの過去についてのテーマ
あなたの過去についてのテーマは、あなたの価値観や行動特性を知るための頻出テーマになります。
具体例:
- 学生時代に(最も)力を入れたこと(ガクチカ)
- これまで最も打ち込んだ経験(継続してきたこと)
- 過去に最も困難であったこと
- 人生で最も感動した経験
- 人生のターニングポイント
あなたの現在についてのテーマ
具体例:
- あなたが人に負けないと思っている強み、チカラ(能力)・長所・性格
- あなたにとって「挑戦」とは何か
- あなたの「座右の銘」
- 最近最も気になったニュース
- 最近最も関心のあること
- 最近最も興味深いと思った本
あなたの現在についてのテーマは、あなたが「現在」をどうとらえているかを通じて「あなたの価値観」と現在持ち得ている強みや能力」をチェックします。あなたの過去の出来事を自己PRの内容の根拠としてチェックする、また、現在の興味・関心がどのように生まれたのかを、過去⇒現在という軸で、あなたを理解するテーマです。
あなたの未来に対するテーマ
具体例:
- あなたにとって仕事とは(私の職業観)
- どのような社会人になりたいか(理想の社会人とは)
- 将来の夢(仕事を通じて、将来実現したいこと)
- 仕事を通じて実現したいこと
- 10年後の自分
- 20年後の自分
- あなたが会社に求めるもの
- 志望動機
あなたの未来に対するテーマは、職業観(職業に対する価値観)と志望動機に深くかかわるテーマになります。過去から未来への一貫性と、企業が求める人材像とのマッチング、志望動機の本気度を中心にチェックします。
この種のテーマの作文の場合の最後、文の結びは「志望する企業のビジネスに帰結させる抱負やビジョン」で締めると印象が高まります。単にあなたの感想を聞いている訳ではないことを意識しておいてください。
上記の「あなたの過去、現在、未来」を問う作文のテーマ以外に、マスコミ企業や総合商社、金融機関等の大企業では、社会性のあるテーマや時事問題に関する「小論文」が加わります。
社会性のあるテーマや時事問題は常に変化しているため、小論文をクリアするためには、日本のみならず世界の全般の社会問題や、経済、時事、旬なトピックに関心を持って、新聞等で基礎的な知識を持っていること、考える習慣がついていることが前提になります。
また、一般企業の場合は、その企業が所属する業界や企業そのものに関するテーマとなる場合もあるため、深い業界研究・企業研究が必要と理解して下さい。
就活のスタートには、自己分析のサポートツールで自分の強みを発見しよう
「自己分析」は就活のイロハの「イ」ですが、時間がかかり大変です。そして自分を冷静に見つめ直すのも難しいものです。
そんな時、力になるのは本格的な適職診断ソフト、「Analyze U+」です。
「Analyze U+」は251問の質問に答える本格的な診断テストで、質問に答えていくと経済産業省が作った「社会人基礎力」を基に、25項目に分けてあなたの強みを偏差値的に解析してくれるものです。
本当のあなたの強みや向いている仕事を素早く「見える化」してくれます。
「AnalyzeU+」を利用するには、スカウト型就活サイト「OfferBox![]() 」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
OfferBox![]() は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
手早く自己分析を済ませ、就活の流れに乗っていきましょう。
選考に強い「作文」を書くにはどうすればよいか
文字数制限の90%以上を基準に書く
エントリーシートや筆記試験で提出する「作文」、「小論文」にはほとんどの場合、文字数制限が設定されています。例えば「800文字以内」という制限の場合、設定された文字数制限内で納めることは当然ですが、90%以上の文字数で書くべきです。(800文字の場合であれば、720文字以上)90%を頭に入れておいてください。
自分自身に「企業が求める人材像」を掛け合わせる
就活における「作文」の内容は、「企業の価値観や求める人材像とのマッチング」をチェック、評価するためのものです。
自分の経験、事実、自分の意見を書くことが大前提になりますが、それをそのまま書くのは「選考に強い作文」にはなりません。
選考は「あなたと企業のマッチング度合い」を測るものなので、企業がどのような価値を生みだしているのか(企業の存在意義)を根本に置いて考える必要があるのです。
企業の顧客にとっての価値が見えれば、おのずとその価値を生むために、どのような価値観を持って企業を経営しているのか(経営理念)が分かります。
企業の存在意義を全うするために、そのベクトル上に集まっている人材の共通の資質、「企業が求めている人材像」があります。
これらの情報は、企業の採用ページ、企業のWEBサイトやIR情報をしっかり研究すれば、必ず明確になる情報です。
文章化されている「求める人材像」が抽象的であっても、採用サイトに必ずと言ってよいほど掲載されている「自社で活躍している社員」、「若手社員の座談会」のコンテンツから、その企業が求めているチカラ・能力の内容を具体的に知ることはできるのです。
たとえば「チャレンジ精神をもって、自発的に行動し、最後まで誠実に、粘り強くやり遂げる人」が求める人材像であった場合、それをあなたに置き換えてみましょう。
上記に挙げられているチカラの中で、あなたに最もあてはまるものは何かを決めて、それを最もアピールできるエピソード(経験・事実)を選び、文章全体で「求める人材像」のイメージに近づくように意識して書きましょう。」
説得力のある書き方を身につける
「作文」の読者は企業の人事担当者や採用担当者です。企業の人気度にもよりますが、彼・彼女らは1日に数百枚のエントリーシートや筆記試験での作文に目を通しています。
従って、ESや提出作文1点に目を通せる時間はとても短いため、ざっと目を通して通過の可否を判定するのです。
そのため、作文で「何を主張したいのか」が分かり難いものは躊躇なく落とされると考えて下さい。
そうならないための「文の基本の構成」があります。
物語の場合は「起承転結」が基本の構成とされていますが、就活の作文ははじめから終わりまで味わいながら精読しないため、結論(主張したいこと)が最後まで読まないと分からないものはNGと考えてください。
就活の「作文」で推奨される基本の構成
就活の「作文」で推奨される基本の構成は「序論」、「本論」、「結論」の3つの構成です。「序論」、「本論」、「結論」の構成は小論文やレポートを書く場合の基本の構成です。このままだと分かり難いので、それぞれに内容をみていきましょう。
- 序論(導入):問題提起・意見の提示
- 本論(展開)):理由・根拠を述べる、例をあげて補強し主張を論証(説得)する
- 結論(結末):結論(まとめ)、対策・解決策、将来へのビジョンの提示
指定されている文字数の制限によって、それぞれの構成に盛り込む要素を若干調整する必要がありますが、基本的にこの型を使いましょう。
就活の「作文」の場合(特にエントリーシートの場合)は文字数が少ないため、以下の構成で良いです。
- 序論:最も伝えたいこと(自分の意見)を結論としてはじめに提示
- 本論:最も伝えたいこと(自分の意見)の根拠を、自分の経験・事実、事例をあげて補強⇒説得力の強化
- 結論:結論(まとめ)を言い変え、対策・解決策、将来へのビジョンの提示で結ぶ
就活の「作文」の目的は、あなたの良さを知ってもらうことです。小論文で文字数が多い場合は別として、800文字以下の制限の場合は「一般論」や「他人の意見」を余裕はないと思います。
あなたの過去・現在・未来に関する設問の場合、一般論は全く必要ないでしょう。他人の意見はエピソードを紹介するのに必要不可欠の場合は最小限の記述で入れる程度です。
「問われている質問・テーマ」に対し、「あなた自身の考え・行動」を「最も伝えたいこと=結論」にして冒頭に言い切る構成を基本にしましょう。
起承転結の4段落構成が有効な場合
小論文や、文字数が多い作文のテーマ、自由回答(文字数制限なし)の場合は、「起承転結」の4段落構成の使用も検討しましょう。
この場合の「起承転結」は、物語で使用されるものではなく、以下のフローが基本型として考えてみてください。
- (起)第一段落:問題の提起・前提となる認識
- (承)第二段落:第一段落に対する自分自身の意見の提示、賛否を明確にする
- (転)第三段落:第二段落の自分の意見の根拠(事実・経験・具体例)による掘り下げ
- (結)第四段落:文全体の論旨から、自分の主張する結論・意見をまとめる
「序論⇒本論⇒結論」の3段落構成でまとめるべきか、「起⇒承⇒転⇒結」でまとめるべきかは、テーマと文字数によってどちらが「腑に落ちる構成」になるかを考えて決めることになります。
ケースバイケースで応用できるように、同じテーマを3段落構成と4段落構成で書いてみる練習もしておきましょう。
正しい作文のプロセスを身につけよう
構成が理解出来たら、具体的に文章を作っていくことになります。
エントリー時での作文でも、筆記試験での作文でも、いきなり頭に浮かんだアイディアを文にするのは止めましょう。非常に効率が悪く、構成が文に引っ張られて、のちに収拾がつかなくなります。
以下に示すプロセスを覚えておきましょう。
- Step 1: 何について書くかのアイディアを出す
- Step 2: 自分が最も伝えたいことを決める
- Step 3: 自分が最も伝えたいことを、どのような構成でまとめるかを決め、構成メモを完成させる
- Step 4: 文章を作成し構成に従って置いてみて、文字数の調整や編集を行う
- Step 5: 文章の校正、誤字・脱字、送り仮名、「です」「ます」「である」調の統一、字数などを確認し完成させる
尚、筆記試験の作文の場合、Step 1の前に、時間配分をしておきましょう。個人差はありますが、時間配分の目安は以下のように考えておいてください。
| 試験時間 | Step1~3 構成メモ作成まで | 解答文章の作成 | 校正・見直し・完成 |
| 30分 | 10分 | 15分 | 5分 |
| 60分 | 15分~20分 | 30分~40分 | 5~10分 |
| 90分 | 20分~30分 | 50分~60分 | 10分~15分 |
マスコミ志望者の場合資料を読み込んで自分の論点をまとめるなど、小論文をまとめるための専門的なノウハウが必要になります。マスコミ志望の方は小論文対策の専門書も数多く出版されているので参考にしてください。
文章の作成で注意すること
「採用試験」の一環であるため、ミスをしないことも重要です。作文で起きるミスをまとめると以下のように類型化できます。
「作文」・」「小論文」におけるミスをしないこと
「作文」・」「小論文」におけるミスは主に以下のパターンに類型できます。
- 誤字・脱字がある
- 主語と述語が合っておらず、ねじれてしまう
- NG例:「私の将来の夢は社長です」
- 主語と述語が不明確で分かり難い
- NG例:「私は将来経営者となり、業績を伸ばすだけではなく、広く社会に貢献することが私の夢です」
- 一文が長く、多くのことを詰め込み過ぎる
- ⇒一つの文で一つのことを伝えるのが基本。一文一義で1文は70文字以内と考えてください
- 漢字の使い過ぎで読み難く、意味も伝わり難い
- NG例:企業戦略立案時に於いて戦術の実行可能性の検証が重要である
- 敬語の使用・不使用が一致していない
- NG例:その時は教授の言っていることが理解できませんでしたが、その後おっしゃっていたことが分かりました。
- 敬語の使用方が間違っている
- NG例:教授にお礼をさせていただきました。
- 文末が不統一
- NG例:「です/ます」調の文と「~だ/である」が入り混じる
- 5W1Hが分かりづらい表現
- NG例:「私はその際○○をすぐ行うべきだと考え、■■を優先するように後輩に指示をして、■■■を達成することができました」
具体的な文を作成する際、構成する際は上記の点をチェックして正しく、読みやすい文章にしていきましょう
読まれるために+アルファの工夫を文章に施そう
文のテーマにもよりますが、「作文」のタイトルを自由に付けられる場合や、文の冒頭、結論部分にアテンションを引く工夫を入れられるかを検討していきましょう。
タイトルや書き出しは、その後の文を読み進んでもらえるかどうかを左右する重要なファクターになります。
例えば「学生時代に最も力を入れたこと」についての作文では、冒頭の表現の違いで、その後を読み進みたくなるかどうかが違ってくるのです。
一例ですが「学生時代に最も力を入れたこと」が、ラクロス部での活動である場合を比較してみましょう。
- Aさんの作文:私は大学3年間ラクロス部に所属し、インターカレッジ大会の準優勝に貢献しました。
- Bさんの作文:ラクロス部在籍3年間で2度の骨折が、インターカレッジ大会での準優勝に結びつきました。
上記のAさんと、Bさんの冒頭の比較では、圧倒的にBさんのほうが 、ラクロスそのものに対する興味や、Bさんの骨折と準優勝の関係を知りたくなりますよね。
これが「表現の工夫」の意味です。
「何を伝えたいか」が決まったら、少なくともタイトルや冒頭の書き出しは、インパクトやアテンションを意識した表現を工夫してみましょう。
文章力を上げる方法
文章力を上げるのは、この記事で解説した基本を意識しながら「練習」をしていくしかありません。
練習をせずにいきなり「良文」は書けません。就活に取り組みはじめたら、できるだけ早い段階で、なんとなくでも良いので具体的に志望したい業界や企業を選んでみましょう。
そしてその企業の過去のESや筆記試験のテーマを練習問題として、文をまとめる練習を積んでいきましょう。
もちろん、闇雲に手を付けるのではなく、自己分析⇒業界・企業研究をある程度進めて、ターゲットの企業を決めて具体的なテーマで書く練習をすることです。
マスコミ志望など、文章表現力が特に必要な業界を志望される方は、早期に専門書や問題集に取り組んでください。
文章力を上げ、筆記試験のスピードに追い付くためには練習量をこなすことが絶対に必要です。マスコミ業界は全体的に難易度が高いので、集中して取り組んでください。
まとめ
- 就活における「作文」とは何かを理解しよう
- 就活「作文」の読者を理解しよう
- 就活「作文」では何をチェックされるのか
- 就活「作文」の類型を理解しておこう
- 選考に強い「作文」を書くにはどうすればよいか
- 文字数制限の90%以上の文字数で書こう
- 自分自身に「企業が求める人材像」を掛け合わせる
- 説得力のある書き方を身につけよう
- 就活の「作文」で推奨される基本の構成を理解しておこう(3段落・4段落構成)
- 正しい作文のプロセスを身につけよう
- 文章の作成で注意すること
- 「作文」・「小論文」におけるミスのパターンを理解して、ミスをしないこと
- 読まれるために+アルファの工夫を文章に施そう
- 文章力を上げる練習をしよう
自己PRが書けない時に!Chat GPT自己PR作成ツールを使おう
自己PRを作成する際、伝えたいことは沢山あっても、上手くまとめる自信がない就活生も多いはず。
そんな時は、「Chat GPT自己PR作成ツール」を活用してみましょう。
就活サービスを提供している、キャリアパークのChat GPT作成ツールを使えば、簡単な質問に答えるだけでAIが作成した理想的な流れの自己PR文が完成します。後は、それを基にブラシュアップするだけ。志望企業の人材像にミートするよう、オリジナリティを加えていきましょう。
無料でダウンロードして、人事を唸らせる自己PRをサクッと完成させましょう。
※またこのツールを利用する際、就活をより効率化できる無料の就活サービスを同時登録することも忘れずに!
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します