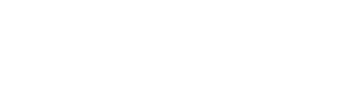Contents
グループワークとグループディスカッションの違い

グループワークとグループディスカッションは、企業側も厳密に定義をして行っていない場合も多く、注意が必要です。
グループワークの特徴は、必ずワークの成果が求められることです。グループディスカッションで、テーマ・課題に対して、必ずその結論と発表を求められる場合は、グループワークと同じと考えて下さい。
この場合は言葉の定義に差はありません。敢えて言えば、グループワークの方が、議論の中身や過程にプラスして、成果物そのものの精度やクオリティが重視されるという点です。
グループワークの中には、ディスカッションより共同作業と、その成果を重視するタイプが含まれます。
例えば、企業のポスターを制作する、キャラクターを制作する、紙によるタワーをその場で作って高さを競う、特殊なカードとルールによる交渉ゲーム、限定された情報から地図を完成させる、計算を駆使して正解を出す、高度なフェルミ推定を使用するものまで様々です。
このタイプはディスカッションとは呼ばず、グループワークと呼びます。議論の内容より、役割分担、作業の段取り、目的を達成するロジック、共同作業、成果物の精度とクオリティ、発表の仕方が評価され、メンバーの貢献度により選考の可否が決まります。
グループワークの進め方
紙やパスタで作るタワーの高さを競うような、作業型のグループワークを除けば、グループワークに共通する進め方があります。しっかり頭に入れておかないと、必ず迷走します。グループワークの進め方をステップごとに解説します。
Step 1: 時間配分を決める

グループワークは、時間内に成果物を仕上げ、発表できる状態にする必要があります。グループディスカッションより、議論をまとめて、発表できるようにするための時間が必要になります。
それを考慮して時間の配分を初めに決めましょう。制限時間は短いので、時間配分を決めるのに時間を使ってはいけません。揉めるようでしたら暫定的に大枠を決めて、スタートして途中で調整する合意をしてください。
制限時間を30分とした場合の標準的な配分は以下の通りです。発表は終了後として、発表そのものの時間は含んでいません。(スマートフォンで読んでいる方はスライドさせてください)
| 定義の合意 | テーマ・課題の内容を定義して合意する | 2分 |
| 解決策のアイディア出し | 課題を解決するためのアイディアを考え、ブレストする | 5分 |
| アイディアの選定 | 解決策・アイディアの分類・整理・まとめ・選定 | 8分 |
| アイディアの具体化とブラシュアップ | 選定したアイディアと実現するための具体策のブラシュアップ | 8分 |
| プレゼン・発表の準備 | 決められたプレゼン形式による、まとめと清書 | 6分 |
| プレゼン練習 | 決められた時間内でプレゼンできるかの検証 | 1分 |
大まかな目安として、アイディアを決めるまでに15分、アイディアを具体策として精緻化し発表までまとめるために15分というイメージです。
Step 2: テーマ・課題の内容を定義して合意する

時間配分を決めて、すぐ各自アイディアを考え始めるのはNGです。メンバー全員で与えられたテーマ・課題の定義を合意することなしにアイディアを出しても、各自の考えのレベルがまとまりません。
例えば「コンビニエンスストアの売り上げを1.5倍にする具体策を考えてください」という課題が与えられた場合、いきなり考え始めると、ある人は都市部の駅前の競合が激しいコンビニをイメージしてアイディアを考えるでしょうし、ある人は郊外の駐車場のあるコンビニを想定してアイディアを出すでしょう。コンビニエンスストアといっても、立地や設備、顧客層によって具体策が違ってきます。
従ってあらかじめ、このグループが対象とするコンビニエンスストアを定義しておく必要があります。典型的な2つのタイプと決めた場合は、メンバーのグループを分けて、それぞれのタイプ別にアイディアを集中的に考えた方が生産的な議論ができます。
Step 3: 課題を解決するためのアイディアを考え、ブレストする

Step 2で定義を決めたら、それに従って具体策のアイディアをどんどん出していくフェーズに移ります。役割分担を決めて、分業制で解決策を考えていきましょう。
前述の「コンビニエンスストアの売り上げを1.5倍にする具体策を考えてください」という例で2つの典型的な店舗形態で考えることに合意した場合は、Aさんは都市型駅前店舗の客数を伸ばす方法を考える、Bさんは都市型駅前店舗の客単価を上げる具体策を考える、Cさんは郊外型ロードサイド店の客数UP,Dさんは客単価UPという分担ができるでしょう。
それぞれの担当分野を決めて集中的にアイディアを考えた方が、あとでアイディアを持ち寄った際に幅ができます。ポストイットの使用が可能であれば、アイディアをどんどん書き出していきましょう。
次に各自アイディアを出し合い、要点だけ発表します。各メンバーはそれを否定せずに、そのアイディアがもっと良くなる点があれば自由にコメントを出していきます。この段階では、議論を活発に出来る雰囲気をつくっていくことが重要です。お互いに自由に発想し意見を言える、オープンな方向で議論を盛り上げて下さい。ブレストの初期段階として、アイディアがどんどん出てくる、ポストイットの枚数が増えていくことを目指しましょう。
アイディアが思いつかない人がいる場合は、思いついた人が「例えば、○○を○○してみるというアイディアはどうですか?」とサポートしてあげましょう。議論に参加できなくても、他のメンバーの意見を傾聴し、賛意を表す、付け加えられそうなことがあればコメントしてみるなどの貢献はできるはずです。
Step 4: 解決策・アイディアの分類・整理・まとめ・選定

ここからが本格的なディスカッションによる、まとめの工程に入っていきます。目の前にはアイディアが書かれたポストイットが置かれています。
この段階でまず行うことはアイディアの分類です。上記のコンビニエンスストアの例で言えば、立地別に客数を上げる、客単価を上げるアイディアが沢山でているはずです。しかしアディアの粒度はバラバラです。実現可能性のあまりないアイディアや、どうかんがえてもコストがかかり過ぎて、1.5倍にするための経済合理性がないものも含まれています。
そこでアイディアを基準に従って分類、整理していく必要があります。共通に括れるものがあれば括っていきます。新メニュー開発、宅急便業者とのサービス連携強化、新プロモーション、シニア向けデリバリーサービスなど、共通で括れる柱を立てていきましょう。
分類・整理ができたら、評価して選定に入ります。売り上げ1.5倍が達成目標のため、客数UPと客単価UPの両方を提案すべきという結論に達した場合、それぞれの具体策をどう組み合わせるか、優先順位をどうするか, 最終的に何案プレゼンするかの選択・決定をします。
選択する際、多数決は使用せず議論によって決めるのが基本です。例えば、実現性とコスト、アピール力の3点で選ぶという基準を設定して選択することがセオリーになります。
Step 5: 選定したアイディアと具体策のブラシュアップ

解決策のアイディアが決まったら、それを実現するための具体的な詰めを行っていく必要があります。アイディアは良くても詳細が詰められていないと、単に「あったらいいな」と夢や希望を語っていることになり、評価されません。
アイディアを具体化する為によく使用されるのが5W1Hに落とし込んで詰めるやり方です。各アイディアに対し以下を当てはめ、書きだしていきます。
- Who: 誰が誰に対して
- What: 何を
- When: いつ
- Where: どこで
- Why: 何故
- How: どうやって (どのくらいの規模・費用で、どのくらいの期間で)
このプロセスでは、全員がどんどん意見を出し合って、フィックスしていくことに集中しましょう。まさにグループ全体の力が試されます。
余裕があれば、具体化する過程で出てきた疑問点や不安な点に対する反論も考えておきましょう。
Step 6: 決められたプレゼン形式による、まとめと清書

最終的に発表する内容を、決められたフォーマットでプレゼンするための、まとめが必要です。よくあるのがB全のプレゼン用ポストイットや、模造紙にマジックでまとめるパターンです。
まとめる時間がなくなってしまうことが頻繁に起こります。その場合、議論の過程で使用したものを使用してプレゼンすることになってしまうため、アイディアがよくても、まとめる力がないと見做されてしまいます。
しっかり発表内容をまとめられる時間をとることが、グループディスカッションと違うところです。発表を上手に、手早くまとめるために以下のフォーマットを頭に入れておいてください。
- 最終的な結論を、結論として大きく書き出す
- アイディアを選んだ理由:定義・アプローチ
- 解決のための具体策:詳細な方法論 (目的・ターゲット・実現可能性)
- 期待効果:解決策が実現した場合の成果 (コンビニの売り上げの場合は具体策の貢献効果の仮説:例えば客数を1.2倍、客単価を1.25倍にして1.5倍の売り上げを達成するための施策をブレークダウンするなど)
- 再度アイディアを簡潔にまとめる
あとは指定された時間内で発表するだけです。この記事で詳細に解説した進め方を頭にいれてグループワークに臨んでください。
「就活の答え」ではグループディスカッションに強くなる思考法やフレームワークも詳しく解説しています。以下の記事も併せて参考にしてみて下さい。
就活のグループディスカッションの実践練習イベント、DEiBA(デアイバ)を試そう
グループディスカッションを経験したことが無い方、経験したことはあるが上手くいかずに悩んでいる方、もっと経験を積んでおきたい方はいませんか?
DEiBA(デアイバ)という就活サービスは、1回15分のグループディスカッションを、1日最大4回も実践練習ができる就活サービスです。就活生の登録料や参加費は完全無料で利用可能です。
既に累計7万人、毎年1万人以上もの就活生がDEiBAのグループディスカッションの実践練習に参加しています。
尚、DEiBAは、オンライン/東京/大阪/名古屋/札幌/仙台/金沢/岡山/広島/福岡で参加が可能ですが、開催場所と日時は毎月異なり、参加人数制限があるため、DEiBA会員登録と開催予定を確認した上で早めのイベント予約が必要になります。
興味が湧いたら今すぐチェック!
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します