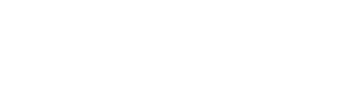新型コロナウイルス感染症の蔓延以降、就活のグループディスカッション選考もオンラインで行うことが一般化しました。
2024年卒の就活からは、ウィズコロナにおいても規制撤廃で社会を回していこうというトレンドになり、大卒新卒時の面接選考も対面に戻す企業も出てきたため、グループディスカッションも今後は再び対面方式に戻っていくことも考えられます。
しかし、特にインターンシップや選考初期段階でグループディスカッションによる選考を行う企業は、可能な限り多くの志望者に参加してもらうという考え方から、オンライン方式を変えていませんし、今後もそのまま定着させる企業がほとんどです。
オンライン開催には、企業側も学生側もオンライン開催は圧倒的に手間がかからず、より多くの回数をこなせる、より多くの就活生に機会を提供できるというメリットがあるためです。
Contents
オンラインでのグループディスカッション(GD)を攻略しよう
「就活の答え」ではリアルなグループディスカッションやグループワークを成功に導く様々なノウハウを提供しています。
特にオンライン グループディスカッション開催の場合、成功に導くためのじぜん準備から本番終了までに行うことを以下の記事で徹底解説しています。
この記事では、オンライン開催直前から本番中に注意すべきポイントをまとめました。
何らかの理由で充分な準備が出来なくても、選考で高評価を獲得するために行うべきことをまとめていますので、チェックリストとして本番に活用してください。
オンライン グループディスカッション実践用チェックリスト
コロナ禍の中で学生生活を過ごしてきた皆さんは、オンラインツールの使用には慣れているので、オンラインでの意見のやり取り、議論に関しては、それほど心配をしていないと思います。
オンラインGDへの参加依頼を受けた時、自分が知らないオンラインツール(企業用の専用ソフト)や慣れていないオンラインツールの場合は、検索して事前に出来るだけ知識を得ておくことです。
オープンなソフトで慣れていない場合は、友人に協力してもらって操作になれておきましょう。
就活の選考に使用される「グループディスカッション(GD)」は独特です。
対面でも難しい選考ですが、オンラインにはオンラインの難しさが加わります。以下の直前対策を頭に入れて、オンラインGD選考を勝ち抜きましょう。
オンラインGDの特徴を理解し、活発な議論を行える雰囲気をつくること
お互いに初対面の学生が、グループで予測できないテーマに関して、いきなり議論をしなければならないというフォーマットであるため、リアルな対面でのグループディスカッションより難易度が高いと考えて下さい。
全く知らない人とあるテーマに関して議論する時、対面であれば参加者の表情やしぐさ、声や発言の仕方、言い方、場の雰囲気を人間の知覚が総合的に判断して、おたがいに阿吽の呼吸のようなものが出来ていくものです。
同じ場を共有していく中で、はじめはぎこちなくても、徐々にお互いが空気を読み合いつつ、自分の意見を言える雰囲気、自分を表現することが自然に出来ていくものです。
オンラインではリアルな対面方式に比べて、この「場を共有する雰囲気」がつくり難いという特徴があります。
参加者一人一人の画面は小さく、その小さい画面から読み取れる情報が限られてしまうため、GDの初心者同士のディスカッションの場合、最後まで議論が弾まない、かみ合わないといったことが起こってしまいます。あるいは殆ど発言できないで終わってしまう参加者が出てしまう事もあります。
オンラインでのディスカッションでは、発言のタイミングが被ってしまうことも起こるため、お互いに「間」をとることも対面より難しくなります。
グループディスカッションでは、チームで議論を活性化して、チームとして最良の結論を得ることが重要であるため、まず参加者全員が活発に発言して、議論を活性化する場としなければなりません。
GDに慣れていて、司会役(ファシリテーション)が上手くできる参加者がいる場合は、その人のファシリテーションに乗っかって、生産的な議論ができることもあります。
しかし、いつもそのよう優れた参加者がいてくれるとは限りません。
ではどうするか?
参加者全員が意見を言いやすい雰囲気をつくることが、まずやるべきことなのです。
自ら司会者(ファシリテーター)を買って出て、上手くやり切れればベストです。
ゼミやサークル活動のリーダー的存在の方は、それほどハードルは高くないでしよう。ファシリテーターとして、全体の議論を盛り上げて、チームとして良好な議論や結論ができれば、あなたに対する評価は高いものになります。
ファシリテーションの経験値があまりない無い場合はどうすれば良いのでしょう?
自分の意見を言ってから、他の参加者個人に意見を聞くフローを心がける
リアルな対面でのディスカッションでは、議論をするという「場の雰囲気」が自然とできていくため、「私はこう思う。何故なら~~~」と不特定多数の参加者に意見を言うだけでも、参加者のだれかがその意見を拾って自然にフォローしてくれたり、反対意見や、その人独自の意見を言ってくれたりと、議論がつながっていきます。
オンラインでは、PCの画面上小さな画面と音声を共有しているだけなので、その段階では無味乾燥でフラットな状況となります。
それでも対面と同じように、誰かが意見を拾って自然に議論がつながっていけばまだ良いのですが、全員が参加者の出方を伺ったり、「変なことをはじめに言ってしまいマイナス評価を受けたくない」と参加者ばかりで議論がつながっていかないということが起こります。
そのような状況になって、チーム全体が沈んで行かないように、「意識的に、特定の人の意見を聞く」という姿勢をとっていきましょう。
指名されても意見がでない場合は、また別の参加者を指名して意見を聞くことです。
対面でのGDでも有効な手法ですが、オンラインで議論が活性化しなさそうな時は特に有効な方法です。
これを行っていくと、自然にファシリテーター的な役割の一部を自然に担うことになり、少なくとも積極的に議論の活性化に貢献する人という評価を得ることができます。
自然に他の参加者に意見を促せるように、参加者の名前を覚えること
対面のGDでは名札や、卓上ネームプレートを見れば意識しなくても個人を指名することは可能です。
Zoom等のオンラインツールでも名前を表示する機能があるため、あらかじめ主催者が名前を表示するように設定している場合はそれに従えば良いだけです。
オンラインで名前が表示されず、主催者である企業担当者が参加者を紹介しない場合、自己紹介やアイスブレークの時間を取らない場合は、GDの冒頭に「簡単に自己紹介しましょう」、あるいは「会議中に呼び合う名前を決めましょう」と発言して、自分の名前(呼び名)を言ってから、参加者の呼び名を全員聞いて、メモしておきましょう。
少しでもアイスブレークが出来るだけで、バラバラな参加者が一つのチームとして議論を行う雰囲気ができるし、名前を呼び合って発言を促す雰囲気が出来ていき、議論が活性化していきます。
発言はカメラ目線で行うこと、はっきり発言すること
オンラインGDではPCの画面(相手の顔)を見ながら発言すると思いますが、みなさんが一般的に使っているノートブックPCを普通に机に直置きして、画面を向いて話すと、話しているあなたは少し下を向いて話している姿が参加者のPCに共有されます。
あなたは相手の目を見ながら話しているつもりでも、参加者や相手には下を向いて話しているように見えてしまいます。
ノートブックPCのカメラを見て話せるように、カメラの位置を自分の目線と正面になるように、高さや角度を調節することを忘れないようにして下さい。
ノートブックPCスタンドを使うと、この調整がしやすくなります。安いスタンドなら2,000円以内で購入できるので、使っていない方は検討してみてください。
またオンライン上の音声は聞きづらい場合や、若干のディレイが起こる場合、または雑音や異音が発生してしまうこともあります。
参加者に自分の音声は正常に聞こえているかの確認をお願いし、参加者の音声も正常に聞こえるかも会議の冒頭でチェックして、うまくいっていない場合はお互いに調整をしてから会議に入りましょう。
発言の際は、語尾を濁したり、声を小さくしたり、「~~~はどうなのでしょうか?」というような曖昧な表現は避けて、「はっきり」ものを言うことを心がけてください。
対面のGDは参加者が空気を読んで、「何となくポイントを理解する」ことができますが、オンラインでは「何となく」がなかなかし難い環境になります。
対面のGDより「はっきり」意見を言うことを心がけましょう。
意見のポイントが「はっきり」伝わるように「結論ファースト」と「理由」で話そう
対面では「何となくポイントが伝わる」ことが、オンラインでは難しくなります。
対面でも「結論ファースト」と「その理由」を話すことはGDでの発言のセオリーですが、オンラインでは更に重要になります。
ディスカッションに慣れていれば、複雑なことはPREP法で話せばより説得力がある意見となりますが、教条的に全てに対応する必要がない、かえって冗漫になってしまう場合もあります。
PREP法
- P: Point=結論(聞かれていることに対する答え)
- R: Reason=理由(何故、上記の結論になるのかの理由)
- E: Example=具体例(結論と理由を裏付け、補強する具体例(データ、数値・客観評価)
- P: Point=結論(結論を別の言葉で言い換え、文を結ぶ)
従って、少なくとも結論を初めに伝え、その理由を答えることをセットにして発言し、具体例は自分の意見を補強するものとして、必ずしも一気に話さず、参加者との議論の中で説明していった方が議論は繋がっていきます。
GDでは、自分を目立たせることを優先し、一気に自分の意見をまくし立てる参加者も出てきますが、評価されるGDは一人が目立つことではありません。
課題が構造的に議論され、参加者(チーム)で生産的、建設的な議論ができることが重要であり、その中で個人としては主体的な役割や、議論への参加を担うこと、チームとして最良な議論や結論を時間内にできることが評価のポイントになることを再認識しておきましょう。
タイムキーパーの役割を担っても発言は活発に
タイムキーパーも大事な役割ですが、タイムキーパーを専業でやる必要がないため、それほど積極的に自薦していく必要はありません。
発言するのが苦手の人はタイムキーパーを買って出てみる手はあります。またその場合でもタイムキーピングしつつ、積極的に発言するようにしてください。
議論の冒頭、メンバーで時間配分を決めたら(あるいは企業側から指定された時間配分を確認して)、それに注意を払って、残り時間や、「まとめましょう」と促すことは重要ですが、それだけを行っても評価は得られません。
短くても良いので自分の意見(同意やフォローを含む)を伝えつつ、残り時間やまとめの促進を行うようにしていきましょう。
また議論があらぬ方向に行きそうになったら、時間を理由にして軌道修正を促していく「監視者」の役割を担うことができれば、高評価を獲得できるでしょう。
オンラインでの書記は対面より難しい、それなりのスキルが必要
意見をまとめ、結論を出すタイプのグループディスカッションでは、書記の役割は重要です。
オンラインでもそれは同じですが、対面と違ってオンラインの場合は参加者各自がとるメモの共有や、自分が書いたメモを途中でシェアして参加者に確認してもらうことがし難いため、難易度が上がります。
自分でとったメモをカメラに映してシェアしても、読み難いため中々良いパフォーマンスを出すのが難しい役割となります。
2画面ディスプレイで、1画面ではオンラインGDを、もう1画面でパワーポイントをつくれるようなスキルがあり、議論を聞きながらタイピングや文章をまとめるのに自信がある人は、処理したドキュメントをオンラインツール上で即時的にシェアすることで評価を勝ち取ることもできるでしょう。
しかしそれが上手く出来る学生は少ないでしょう。
どうしても書記の役割が必要で、成り行きで役割が振り当てられそうになったときは、できる限り簡潔にポイントをまとめることと、「自分でまとめたものを発表する発表者」の役割を最後に行えるように、参加者の同意を得ていきましょう。
また、議論への参加は「今までの議論のポイントをまとめると、~~~ということで良いですか」と、合間、合間で、重要ポイントの自分の総括をシェアして、確認していくことを心がけてください。
就活のグループディスカッションの実践練習イベント、DEiBA(デアイバ)を試そう
グループディスカッションを経験したことが無い方、経験したことはあるが上手くいかずに悩んでいる方、もっと経験を積んでおきたい方はいませんか?
DEiBA(デアイバ)という就活サービスは、1回15分のグループディスカッションを、1日最大4回も実践練習ができる就活サービスです。就活生の登録料や参加費は完全無料で利用可能です。
既に累計7万人、毎年1万人以上もの就活生がDEiBAのグループディスカッションの実践練習に参加しています。
尚、DEiBAは、オンライン/東京/大阪/名古屋/札幌/仙台/金沢/岡山/広島/福岡で参加が可能ですが、開催場所と日時は毎月異なり、参加人数制限があるため、DEiBA会員登録と開催予定を確認した上で早めのイベント予約が必要になります。
興味が湧いたら今すぐチェック!
まとめ
今までの重要ポイントを箇条書きでまとめておきます。直前のチェックリストとして活用して下さい。
- オンラインGDの特徴を理解し、活発な議論を行える雰囲気をつくること
- オンラインではリアルな対面方式に比べて、この「場を共有する雰囲気」がつくり難い
- 自ら司会者(ファシリテーター)を買って出て、上手くやり切れればベスト
- 自分の意見を言ってから、他の参加者一人に対して意見を聞くフローを心がけること
- 自然に他の参加者に意見を促せるように、参加者の名前を覚えること
- 発言はカメラ目線で行うこと、はっきり、明瞭な声で発言すること
- 意見のポイントが「はっきり」伝わるように「結論ファースト」と「理由」で話そう
- タイムキーパーの役割を担っても発言は活発に行おう。フォローの発言や監視者としての役割を担おう
- オンラインでの書記は対面より難しい、それなりのスキルが必要。発表者として最後のまとめの発言をしよう
繰り返しになりますが、グループディスカッションは、課題が構造的に議論され、参加者(チーム)で生産的、建設的な議論ができることが評価の大前提です。
その中で個人としては主体的な役割や、議論への参加を担うこと、チームとして最良な議論や結論を時間内にできることが評価のポイントになることを再認識しておきましょう。
発言しないで終わってしまう事は絶対に避け、多少自信が無くても自分の意見を言って、議論に参加することです。
難しければ、他の参加者の意見に対する自分の考えを発言し(フォローや、賛同、別の見方や考え方を含む)、更に議論が繋がるように「〇〇さんは、どう考えますか」と議論を繋いでいくことを最低限行いましょう。
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します