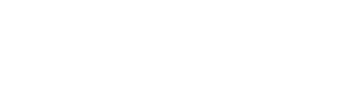就活の一般ルート広報・エントリー解禁(3月1日)が迫ってくると、気になるのがエントリーシートの存在です。
エントリーシートは就活プロセスの第一関門であるばかりではなく、幾重の選考を通過し最終面接まで使用される非常に重要なドキュメントです。
その第一関門であるエントリーシートの選考を通過しなければ、その企業への就活はそこで終了してしまいます。
この記事ではエントリーシートに書く内容ではなく、書き方・文法を解説します。
あなたが優秀な学生であったとしても、あなたの素晴らしさがエントリーシートに上手く書かれていなければ、人事や選考を担当する社員に伝わりません。
エントリーシートに書く内容も重要ですが、書き方がダメだと読んでもらえません。
書き方やES独特の文法をマスターして、第一関門を突破しましょう。
Contents
- 就活人気の高い企業は、「あなたに興味がない」ことが前提
- エントリーシートを読んでもらうための書き方
- エントリーシートを書く時の注意点
- 選考に強いエントリーシートの文章構成と書き方
- 自分がその答えで最も伝えたいことを決める
- いきなり書き始めず、PREP法で答えの骨子をまず作る
- 聞かれていることに、正しく冒頭で答える結論ファースト
- 読み易く、分かり易い文章にする
- エピソードは5W1Hを整理する
- 文字数が少ない場合や簡単な質問に対する答えは「結論→理由→(結論)(冒頭の結論を言い換え文をまとめる)」で書く
- 抽象表現はできるだけしないで、具体的に書く。データや数字、客観的な評価で表現する
- 文字数が多い場合は、理由(背景・目的を含む)と具体例を詳しくして肉付けする
- 出だしの1文にインパクトを出し、印象に残る表現を工夫する
- 文章を作成し、推敲・校正を行い仕上げる
- 可能であれば、第三者の評価を受け、改善点があれば反映する
- エントリーシートの書き方の基本をマスターしたら、自分なりのアレンジを加えよう
- まとめ
就活人気の高い企業は、「あなたに興味がない」ことが前提
数千、数万という志望者が殺到する就活人気の高い企業は、「あなたに興味がない」ことを前提にする必要があります。
志望者が非常に多い殆どの企業は、集まったESを1枚1枚丁寧に最後まで読み切って選考の結果を決めている訳ではありません。
ESを判定する社員のリソース(人数とかけられる時間)は限られているため、ESをななめ読みして判定するのです。
企業によっては外部の人材企業に一部のESの判定を委託している場合すらあるのです。
好意を寄せている人からのラブレターのように、興味があれば一字一句、目を皿のように読むでしょう。
冷たい言い方かもしれませんが、ESをななめ読みしている時点で、残念ながら「あなたに、特別な興味はない」のです。少なくても、あなたは One of 数千、数万の存在というのが現実です。
従って、ESに書く文章は、ななめ読みしても内容がすぐ理解でき、イメージが湧く文章でなければなりません。
選考担当者がななめ読みしても、ESの各質問に対する答えが頭に入ること、イメージが湧くことが極めて重要なのです。
志望者の絶対数があまり多くない企業であれば、集まったエントリーシートを丁寧に読んでくれるでしょう。
その場合でも文章が読みやすく、質が高ければ選考通過の確率は高まります。どんな場合でも、「読んでもらう」ことがはじめの一歩です。
読んでもらえるエントリーシートの書き方をマスターしていきましょう。
エントリーシートを読んでもらうための書き方
エントリーシートを読んでもらうために、最低限守るべき書き方があります。
この書き方ができていないと、どんなに内容が優れていても最後まで読んでもらえない可能性が高まります。
それでも高学歴の学生であれば、ESは通過できる場合もあります。
しかし、適切に文章を作成している同じように高学歴の学生とは差がつきます。ESは通過できたとしても、次のステップで面接官がESを読んだ時には低い評価になるでしょう。
高学歴の学生でもESをあなどってはいけません。
まず就活生全員がおさえておくべき、基本の書き方をマスターしましょう。
エントリーシートを書く時の注意点
- 文字数制限90%以上100%以内を目指す。(80%以上はマスト)
- 余白をできるだけなくす(書くことがなくてもスカスカは本気で志望していない学生とみなされ、即落ちするリスク大)
- 手書きのESの場合は、文字そのものを丁寧に書き、行の曲がりをなくす。全体が読み易く、キレイにレイアウトされた仕上がりになるように、PCで作文して推敲し鉛筆で下書きした後の完成形をボールペンで転記すること。見た目だけで落とす担当者もいるので注意!
- 誤字・脱字を絶対になくすのは基本中の基本
- 悪い例:消費材の生産制に対する研究を行ってきました。
- 良い例:消費財の生産性に対する研究をしてきました。
- 一文を句読点で繋げて多くのことを詰め込まない。一文の長さを40字から50字が目安
- 悪い例:◯◯部のサブリーダーとして、リーグ最下位という屈辱から降格を味わったチームを立ち上がらせ、再び昇格するまで中心となり改革を進めました。(67文字)
- 良い例:◯◯部のサブリーダーとして、リーグ最下位の屈辱を味わい降格となったチームの改革を進めました。(46文字)その結果チームを再び昇格させることができました。(23文字)行った改革は・・・
- 主語が何かを明確に分かり易くする
- 悪い例:私は将来経営者となり、業績を伸ばすだけではなく、広く社会に貢献することが私の夢です。
- 良い例:私の将来の夢は、経営者になることです。業績を伸ばすことで広く社会に貢献したいです。
- 一文に主語は一つにする。その主語に対する述語は一つが基本。多くても二つ迄
- 悪い例:私の将来の夢は、営業として成長して優れた実績を残し、会社をリードする人材になることです。
- 良い例:私の将来の夢は、営業として優れた実績を残し、会社をリードする人材になることです。
- 主語と述語の対応を正確にする。主語と述語のねじれはNG
- 悪い例:私の将来の夢は社長です。
- 良い例:私の将来の夢は、社長になることです。
- 文末を統一する(「です/ます」調の文と「~だ/である」が入り混じるのはNG)
- 悪い例:私の強みは厳しい状況でも、決めた目標を諦めずに最後までやりきる目標意識の高さである。その強みはTOEICのスコアを3ヵ月で300点アップさせ、900点を達成したことにも表れています。
- 良い例:決めた目標を諦めずに最後までやりきる目標意識の高さが私の強みです。TOEICのスコアを300点アップする目標を立て、3ヵ月集中して取り組んだ結果900点を達成しました。
- 注意:「です/ます」調を基本とし、業種・職種・過去の内定者のES、文字数制限によって「~だ/である」の使用を検討。人相手のサービス業と、技術系研究開発分野の専門職へのESでは、適切な文章のトーン&マナーが違います。
- 敬語を使用する場合は正確に使用し、使用する、使用しないを混ぜない
- 悪い例:教授にお礼をさせていただきました。
- 良い例:教授にお礼を申し上げました。
- 悪い例:その時は先輩の言っていることが理解できませんでしたが、その後おっしゃっていたことが分かりました。
- 良い例:私は、先輩の言っていることが理解できませんでしたが、その後になって意味を理解しました。
- 短い文章で多くのことを伝えようとして漢字を使い過ぎない
- 悪い例:企業戦略立案時に於いて戦術の実行可能性の検証が重要である。
- 良い例:企業戦略を考える際は、実施できる戦術の検証が重要です。
- 一部の人しか理解できない専門用語、略語、外国語は使用しない
- 悪い例:バイト仲間とはスマホで連絡をしていました。
- 良い例:アルバイトの同僚とはスマートフォンで連絡をしていました。
- 悪い例:〇〇〇がイッシューでした。
- 良い例:〇〇〇が課題でした。
- 5W1Hを表現する場合は分かり易く書く
- 悪い例:私はその際○○をすぐ行うべきだと考え、■■を優先するように後輩に指示をして、■■■を達成することができました。
- 良い例:私は△△の際○○をすぐ行うべきだと考えました。後輩には■■を優先するように指示をした結果、■■■を達成することができました。
- 話し言葉はNG。社会人としての表現を意識して書く
- 悪い例:すごくリアルに感じました。
- 良い例:現実のような感覚を持ちました。
- 接続詞を多用しない(そして、しかし、また、その上、さらに、等の接続詞は極力使用しない)
- 悪い例:私の就活の軸は、将来〇○○として◇◇◇に貢献し、さらに□□□を実現することです。また私は△△△というビジョンをもっています。しかし、そのビジョンの実現は・・・・。
- 良い例:私の就活の軸は、将来将来〇○○として◇◇◇に貢献することです。□□□を実現して、ビジョンである△△△を・・・・。
- 同じ語尾を続けない。3つ以上連続は出来る限り避けよう
- 注意:ESでは過去の経験や事実、エピソードを答える質問が多いため、自然と「~~ました。」に表現が多くなってしまいます。2つ連続する程度は普通にありますが、3つ、4つと連続していくとメリハリのない文章になり、何を主張したいのかが分かり難くなるので注意してください
- 悪い例:私がアルバイトをしていたイタリアンレストランは、客数の減少に悩んでいました。私は自主的にお客様にアンケートをとった結果、ピザの種類が少ないことが原因であることが分かりました。そこで私はオリジナルのピザメニューを店長に提案しました。3種類の新しいピザをメニューに加え、客数を20%増加させることができました。
- 良い例:私がアルバイトをしていた○○市の「〇〇〇」というイタリアンレストランは、客数の減少が問題でした。そこで自らお客様にアンケートをとって分析した結果、ピザの種類の少なさに不満があることが分かりました。オリジナルのピザメニューを店長に提案し、3種類のピザをメニューに加えた結果、僅か1ヵ月で客数を20%増加させることができたのです。
- 注意:ESでは過去の経験や事実、エピソードを答える質問が多いため、自然と「~~ました。」に表現が多くなってしまいます。2つ連続する程度は普通にありますが、3つ、4つと連続していくとメリハリのない文章になり、何を主張したいのかが分かり難くなるので注意してください
- あいまいな表現はしない
- 悪い例:私は自分でもリーダーシップがあるほうだと思っており、友人からもそう評価されています
- 良い例:私の強みはリーダーシップです。リーダーとして動くことが多く、友人からも同じ評価を受けています。
上記は基本中の基本です。
ChatGPT等のAIのサポートでESの回答を作成する場合のチェックポイントとしても重要です。特にあなたのエピソードが複雑な場合は要注意です。
基本的な注意点を理解できたら、次は選考に強い文章の構成をマスターしていきましょう。
選考に強いエントリーシートの文章構成と書き方
選考に強いエントリーシートの文章構成と書き方をマスターしていきましょう。
選考担当者がななめ読みしても、ESの各質問に対する答えが頭に入り、イメージが湧く文章構成のポイントは以下の通りです。
- 自分がその答えで最も伝えたいことを決める
- いきなり書き始めず、PREP(プレップ)法で答えの骨子をまず作る
- 聞かれていることに、正しく冒頭で答える結論ファースト
- 読み易く、分かり易い文章にする
- エピソードは5W1Hを整理する
- 制限文字数が少ない場合や、簡単な質問に対する答えは「結論→理由→結論(文をまとめる)」で書く
- 抽象表現はできるだけしないで、具体的に書く。データや数字、客観的な評価で表現する
- 制限文字数が多い場合は、理由(背景・目的を含む)と具体例を詳しくして肉付けする
- 出だしの1文にインパクトを出し、印象に残る表現を工夫する
- 文章を作成し、推敲・校正を行い仕上げる
- 可能であれば、第三者の評価を受け、改善点があれば反映する
順番に解説します。
自分がその答えで最も伝えたいことを決める
例えば、「自己PRをしてください」という設問であれば、この企業に対して最も伝えたいアピールポイントは何かを決めましょう。
自己PRの場合、文字数が少なければ一つに絞りましょう。文字量が多い場合でもメインのポイントを一つにしぼり、他のアピールポイントがあれば最後に加える (その場合でも全部で最大3つまで。それ以上は散漫になるのでNG)
取り上げるアピールポイントは、読み手が疑問を抱くような相反する長所や強みにならないように注意して下さい。「物事を深く考える慎重さ」と「フットワークの軽さ」は、それが事実であったとしても違和感の方が先に伝わってしまうものです。
あなたが、どうしても矛盾する内容を伝えたい場合は、矛盾や相反の印象を与えないような工夫が必要であり、それを限られた文字数の中で表現するのは非常に難しいものです。
上記の例で言えば、「物事を深く考える慎重さ」と「熟考に基づく行動力」であれば何とか成立するでしょう。
ただし、エピソードによって証明することが必要になります。
選んだアピールポイントを最も分かり易く、かつ説得力をもって伝えられるエピソードを決めましょう。
いきなり書き始めず、PREP法で答えの骨子をまず作る
最も伝えたいこととエピソードが決まってもいきなり書き始めてはいけません。まずPREPに落とし込んで整理しましょう。
PREPとは伝えたいことを分かり易く伝えるための、文の構成要素と順番であり、その要素の頭文字をとったものです。
- P: Point=結論(聞かれていることに対する答え)
- R: Reason=理由(何故、上記の結論になるのかの理由)
- E: Example=具体例(結論と理由を裏付け、補強する具体例(データ、数値・客観評価)
- P: Point=結論(結論を別の言葉で言い換え、文を結ぶ)
PREP法はエントリーシートの記述のみではなく、面接の答え方の基本であるため、就活生なら必ずマスターしておくべきノウハウです。
この順番で文章を書き、面接で答えると自然と論理的な主張になり、メッセージが頭に入り易いのです。
聞かれていることに、正しく冒頭で答える結論ファースト
PREP法をマスターしていれば、自然と「結論ファースト」で答えられます。
重要なのは、その結論の文は複雑にしないで、分かり易く聞かれたことに対して正しく答えることです。
例えば「あなたが当社を志望した理由を教えて下さい」という設問の場合は、「私が貴社を志望する理由は〇〇〇です」というフォーマットにはまる内容が基本になります。
この志望理由を聞いいている質問では、「理由を聞いているので、冒頭Pの結論は理由」になります。2番目のR(理由)は、その志望理由に至った背景や目的として捉えれば良いのです。
3番目のE(具体例)は2番目の理由を、更に分解して具体的に表現します。結論や理由を具体的な例、データ、数字、客観視点で補強して信憑性を増す機能です。
4番目のP(結論)は、はじめのP(結論)を言い換えて、文全体を結びます。
上記を使用して書かれた志望動機の例文をあげておきます。
例文:トヨタ自動車への志望動機 (400文字)
トヨタの志望理由とやりたい仕事について教えてください。
結論P:
トヨタ車を通じてより良い未来に貢献したいと強く思ったのが私の志望する理由です。貴社は世界の人々の暮らしに最も影響力を持つ、日本のグローバル企業であるため志望しました。
理由R:
車は三万点にも及ぶ部品の集大成であり、産業としての影響力も大きく、その成功は多くの人の血の滲むような努力と想いの上に出来上がっています。それを産み出し世界中の人々に届ける使命、安全性や環境への責任があり、そこに大きなやりがいを感じます。
具体例E:
学生時代、経営学部で国際会計を学び、インドへの進出企業インターンとして1年間現地にて車の部品工場のコーディネーターをした経験を活かして、貴社のグローバルマーケティングの一端を担いたいと考えました。
結論P:
数年間は日本で貴社の一員としての基礎力を付けた後、海外マーケットでの生産やマーケティングに携わりたいと考えています。トヨタ車を通じて世界を豊かにして、日本という国の発展を支えたいと考えます。
エントリーシートの作成に慣れてくれば、あえて少し崩しを入れてインパクトを加えることもできますが、慣れないうちは、結論ファーストで分かり易く書くことを心がけましょう。
読み易く、分かり易い文章にする
PREP法でまとめた要素を、前後の流れ、文脈、表現に気を配りながら、すんなり分かり易い文に直していきましょう。
この記事の前半で解説した注意点を守れば読み易く、分かり易い文章になります。PREP法を応用すれば、ロジカルで説得力のある文章構成になります。
エピソードは5W1Hを整理する
書くべきエピソードを整理する段階では、「誰が、いつ、どこで、何を、何故、どうやって」の要素を考えて要素を出しておきます。
しかしそれをそのまま文章にすると、小学生が書いたような文になってしまいます。または非常に長く、冗漫でポイントが見つけにくい文章になってしまいますので、あくまではじめに要素の整理をしておくだけです。
エピソードを書く場合は、時系列で起こったことを整理してから、次のフォーマットを使って文章にまとめてみましょう。
エピソードを時系列でそのまま書くと、正確に書こうとして文が長くなり、かえって焦点が分かり難くなります。
- 最も伝えたいことを結論として簡潔に述べる
- エピソードの背景・前提となる情報:話の場の設定をして、何について語るのかをはっきりさせる
- そこにあった問題や課題:解決すべきものを初めに述べる
- 問題・課題を解決するためにとったアプローチと目標:分析・気づき・考え方(行動原理)→目標設定まで
- 実施した解決策の具体例:抽象表現ではなく、実際の行動がイメージが湧くようにできるだけ具体的に述べる
- 解決策を実施した結果:データや数値で表現できるものはする。データや数値で表現できないものは客観評価や視点を入れる。その結果学んだこと、今後の活かし方も結論として述べる
上記を意識して書かれたガクチカの例をあげておきます。
例文:学生時代最も力を入れたことを教えてください
万年下位のフットサルチームを引っ張り、リーグ3位を達成しました。当初サークルは上下関係が厳しく、チームの一体感がないことが課題でした。私はサークルのサブリーダーとして、先輩後輩の垣根を越え活発に意見を交換できる練習方法を開発しました。具体的には練習中と練習後に意見交換の場を設けたのです。私が司会をして意見を促し、まとめ、その結論を記録していきました。改善点をまとめたメモを作り、次の練習で全員に配布して練習に反映したのです。その結果、今まで勝てなかった上位チームにも勝利し、万年下位からリーグ3位へのランクアップを実現できました。この経験から、自ら人間関係の接点となり、チームの課題を解決する重要性を学びました。ビジネスでも、チームの目標を達成するために主体的に働きかける人材となることを目指します。
この例文の経験の内容そのものは、特別に凄いものではありません。
しかし文章では、議論の活性化、議論や改善策のまとめ、情報の共有化や定着への工夫など、ビジネスに重要な要素が上手く盛り込まれ、読み易く簡潔にまとめられています。
読み手にとって、起こったことがすんなりとイメージできることが、高評価に繋がります。
文字数が少ない場合や簡単な質問に対する答えは「結論→理由→(結論)(冒頭の結論を言い換え文をまとめる)」で書く
文字数制限や、書き込めるスペースの制約で回答できる文字数が少ない場合の対処法です。この場合は、結論→理由は必須であり、最後に結論を言い換えて文を結ぶ構成を使いましょう。
「私はチョコレートが好きです。何故なら勉強で頭を使うことが多いため、脳が疲れたときに脳への血流を増やす効果があるためです。気分転換にもなるためチョコレートは私の学習の友です」という構造になります。
この構造を志望動機に使用した例文をあげておきますので参考にしてください。
例文:味の素の志望動機の例:
あなたが当社にエントリーする理由を記述してください。(150字以内)
結論:食によって、人の健康と幸福に貢献したいからです。
理由:高校の英語の授業で、”you are what you eat” というフレーズを知り、それ以来偏食を克服し、健康的な生活を取り戻した経験があります。
結論:貴社のEat Well, Live Well. のスローガンと同じく、発展途上国も含め、世界市場で貴社の製品を通じて、人々の健康と幸せな生活に貢献したいと考え志望しました。
抽象表現はできるだけしないで、具体的に書く。データや数字、客観的な評価で表現する
以下の記述を比較してみて下さい。
- A:私が所属するフットサルチームは、○○リーグでも常に上位にランクしていました。
- B:私はフットサルの練習を毎日2時間欠かさず行ってきました。チームは〇〇リーグで常に3位以上の成績でした。
Aはチームが主語になっており、かつ上位ランクという抽象表現を使っているため印象に残らず流れてしまいます。
Bは志望者が主語になっており、毎日2時間という具体的な数字によって努力が表現されています。またチーム成績も常に3位以上とAに比較して明確です。Aに比べ志望者のアピールしたいこと(練習を地道に継続した努力と人柄)と、志望者のイメージが鮮明になっています。
ガクチカや自己PR欄のエピソードでは「その結果、アルバイトをしていた〇〇店の売り上げを〇〇%増加することができました」、あるいは「サークルへの参加率を〇〇%に上げることができました」という具体例が頻繁に出てきます。
それが事実であれば書いて良いですが、その数字やデータそのものにはそれほど意味はありません。
結果は客観的な指標で書けるところは書くべきですが、人事や採用担当者がみているのは、その活動の難易度とあなたの取り組み、プロセスです。
数字やデータはそれを知るためのものであり、達成した%そのもので合否が決まるものではないことを理解して下さい。
「○○を◇◇で〇〇%まで増加するすることができました」と自慢されても、評価者は「ありきたりなES」の1枚という評価をします。
大切なのは「あなたが考え、行動したこと」、「その結果から学んだこと」のなかに、あなたの仕事へのポテンシャルが感じられるかです。
データやア数字は大事ですが、それを誤解しないようにして下さい。
文字数が多い場合は、理由(背景・目的を含む)と具体例を詳しくして肉付けする
以下の太字にした部分が肉付けした部分です。参考にしてみて下さい。
万年下位のフットサルチームを引っ張り、リーグ3位を達成しました。当初サークルは上下関係が厳しく、チームの一体感がないことが課題でした。先輩と後輩はそれぞれ別のグループで意見を出し合っており、試合になると連携が上手く機能していなかったのです。私はサークルのサブリーダーとして、先輩後輩の垣根を越え活発に意見を交換できる練習方法を開発しました。具体的には練習中と練習後に意見交換の場を設け、練習中に10分間、最後に1日の練習のフィードバックを10分間でまとめます。私が司会をして意見を促し、その結論を記録していきました。改善点をまとめたメモを作り、次の練習で全員に配布して練習に反映していきます。その結果、今まで勝てなかった上位チームにも勝利し、万年下位からリーグ3位へのランクアップを実現できました。この経験から、自ら人間関係の接点となり、チームの課題を解決する重要性を学びました。ビジネスでも、チームの目標を達成するために主体的に働きかける人材となることを目指します。
出だしの1文にインパクトを出し、印象に残る表現を工夫する
上記のフットサルのガクチカの例を使うと以下の改善ができます。
- A:万年下位のフットサルチームを引っ張り、リーグ3位を達成しました。
- B:万年下位のフットサルチームを、短期間で3位する方法を開発しました。
Aでも決して悪くはありませんが、Bの方が先を読んでみたくなる表現になっています。あなたの書いたエントリーシートの選考通過の確率をモニターしながら、悪い場合は出だしのインパクトや「何だろう」と思わせる表現も試してみましょう。
文章を作成し、推敲・校正を行い仕上げる
一回、初めから終わりまで通した文章が出来ても、それで終わりではありません。前述した基本として注意するポイントをチエックしましょう。
選考に強い書き方で、文の趣旨、論理展開がスムースに読み易い構成になっているか、具体性や説得力はどうか、など推敲して改善できるポイントは沢山あります。
最後に誤字脱字がないように、文字校正も行って下さい。
可能であれば、第三者の評価を受け、改善点があれば反映する
自分で書き上げた文章を自分で評価し、改善するのは結構難しい作業です。校正も同じです。
なぜなら自分としてはベストと思って書いているために、自分では気が付かないことが多いのです。単純な誤字・脱字も結構見逃してしまうものです。
時間的に可能であれば、必ず信頼のおける第三者、友人、OB/OG、近親者、キャリアセンターの職員、就活サービスのキャリアアドバイザーやコンサルタントに目を通してもらいましょう。
ここまでできれば、かなり精度が上がったエントリーシートを提出できます。
大変な作業のように思えますが、本当に大変なのは最初の1枚を仕上げるときだけです。
あとはその基本形をもとに、質問に応じて変化させれば良いのです。
はじめにベストな基本形をつくれば、ほとんどのES作成作業の60~70%をそれでカバーできると思います。
書きなれてくればコツがつかめてスピードも、文章力も上がっていきます。それでも結構大変ですが、毎回ゼロから作る時間はないないため、はじめのESを出来るだけ時間をかけ、精度を上げておくことが効率的なやり方です。
エントリーシートの書き方の基本をマスターしたら、自分なりのアレンジを加えよう
エントリーシートの書き方の基本をマスターしたら、カタチにとらわれないで、自分が伝えたいことを強調する工夫をしてみましょう。
PREP法は優れた構造ですが、多くの学生が使用しているためエントリーシートの同質化のリスクも考えるべきなのです。
就活当初は、自分の体験・エピソードを掘り下げ、そこに自分だけのオリジナリティを込めていきましょう。
「守破離」という言葉もあるように、何かをマスターする際は、はじめはそれを守り、習熟していくうちに自分なりの工夫を加えて破っていき、最終的には自分で習ったものを更に高次元のものにしていくという考え方です。
エントリーシートの基礎をマスターした上で作成に慣れたタイミングでは、選考結果も踏まえつつ自分なりのアレンジや工夫を入れていきましょう。
それが本当のあなたらしさ、あなたの強みを伝えることに繋がっていきます。あなただけの強いESをつくっていきましょう。
まとめ
就活人気の高い企業は、「あなたに興味がない」ことを前提にESを作成すること
エントリーシートを読んでもらうための書き方をマスターしよう
エントリーシートを書く時の注意点
- 文字数制限90%以上100%以内を目指す。(80%以上はマスト)
- 余白をできるだけなくす(書くことがなくてもスカスカは本気で志望していない学生とみなされ、即落ちするリスク大)
- 手書きのESの場合は、文字そのものを丁寧に書き、行の曲がりをなくす。全体が読み易く、キレイにレイアウトされた仕上がりになるように、PCで作文して推敲し鉛筆で下書きした後の完成形をボールペンで転記すること(見た目だけで落とす担当者もいるので注意!)
- 誤字・脱字を絶対になくすのは基本中の基本
- 一文を句読点で繋げて多くのことを詰め込まない。一文の長さを40字から50字が目安
- 主語が何かを明確に分かり易くする
- 一文に主語は一つにする。その主語に対する述語は一つが基本。多くても二つ迄
- 主語と述語の対応を正確にする。主語と述語のねじれはNG
- 文末を統一する(「です/ます」調の文と「~だ/である」が入り混じるのはNG)
- 敬語を使用する場合は正確に使用し、使用する、使用しないを混ぜない
- 短い文章で多くのことを伝えようとして漢字を使い過ぎない
- 一部の人しか理解できない専門用語、略語、外国語は使用しない
- 5W1Hを表現する場合は分かり易く書く
- 話ことばNG。社会人としての表現を意識して書く
- 接続詞を多用しない(そして、しかし、また、その上、さらに、等の接続詞は極力使用しない)
- 同じ語尾を続けない。3つ以上連続は出来る限り避けよう
- あいまいな表現はしない
選考に強いエントリーシートの文章構成と書き方
- 自分がその答えで最も伝えたいことを決める
- いきなり書き始めず、PREP(プレップ)法で答えの骨子をまず作る
- 聞かれていることに、正しく冒頭で答える結論ファースト
- 読み易く、分かり易い文章にする
- エピソードは5W1Hを整理する
- 文字数が少ない場合や簡単な質問に対する答えは「結論→理由→結論(文をまとめる)」で書く
- 抽象表現はできるだけしないで、具体的に書く。データや数字、客観的な評価で表現する
- 文字数が多い場合は、理由(背景・目的を含む)と具体例を詳しくして肉付けする
- 出だしの1文にインパクトを出し、印象に残る表現を工夫する
- 文章を作成し、推敲・校正を行い仕上げる
- 可能であれば、第三者の評価を受け、改善点があれば反映する
エントリーシートの書き方の基本をマスターしたら、自分なりのアレンジを加えよう
何度も言いますが、ES選考の通過なくして、その先はありません。
就活本番になると本当に、時間がありません。
部分的にAIのサポートを借りて基本形を作成しても良いですが、必ず本当の自分のエピソードにしてリライトすることが必須です。そのまま流用しても、評価者の感情は動かすことはできません。
汎用的なオープンESでも良いので、自分の基本形は早めに完成させて、そこから改善をしていきましょう。
25年卒の就活に即効:ES88,000枚や企業の選考状況、働く社員のコメントが口コミが無料で見放題
「就活の準備に出遅れてしまったかな・・・」、「ES提出まで時間が限られているので、ピンポイントで参照できないかな・・・」、「大手ナビサイトだけで大丈夫かな・・・」、「ES選考に通るためのポイントが分からない」、「この会社って実際のところ、どんな感じなのかなぁ?」と悩んでいませんか?
就活のはじめのハードルがエントリーシートです。ESが通らないとその先はありません。
就活に関する色んな不安を感じたら、134,157枚にも及ぶESと選考体験記が閲覧できる口コミ情報サイト「就活会議」を利用する方法があります。
選考を突破、内定した先輩の実体験が詰まった口コミによって、効率的に選考の準備を進めることが可能です。「就活会議」に登録するだけで、もちろん完全無料で閲覧できます。
「就活会議」の特徴は、先輩達や就活生自身による口コミ就活情報サイトです。
就活生達が書いて選考を通過できた本物のエントリーシートや選考状況の口コミ、納得のいく内定を獲得した先輩達のES、面接選考の体験談、そして実際に働いている社員や元社員の評価まで、すべて無料で閲覧できます。
\\\ 就活会議への登録は公式ページへから ///
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します