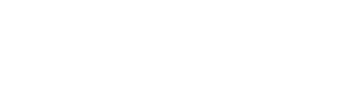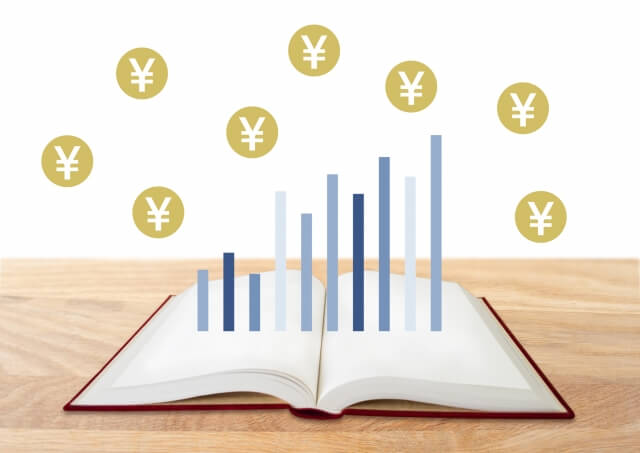Contents
本音では聞きたい給与の話
就活の企業研究を行う際、本音ではとても気になるが給与、年収の額です。「給与の額や昇進、昇格はどう決まるのか」は、本当は重要な情報です。
新入社員として入社した時点でもらえる初任給は採用ページの募集要項で調べることができますし、30歳時点での平均賃金、平均年収と基準になる年齢は東洋経済新報社の就職四季報で概要を知ることができます。
給与や年収の件は、OB/OG訪問でも聞きにくい質問です。
非常に関係が深く、親しいOB/OGがいればフランクに聞けないこともないのですが、一般的には「給与や福利厚生」に関しては「聞かないほうが良い質問」とされています。
会社説明会や一般の採用の広報が解禁された後でも、書いてある以上のことを聞くのは「やる気を疑われる」という恐れもあるため、面接においても「聞くべきではない」質問とされています。
唯一聞けるタイミングとしては最終面接後に人事担当者に質問できる機会がある場合や、人事担当者から条件面の説明を受けた際にする逆質問ぐらいでしょう。
本当は一番知りたい給与体系や人事評評価(考課)制度は、内定式や実際に入社するまでは、限定的な情報しかなく、全体像はブラックボックスになっているのです。
これは企業の給与体系と人事評価システムは本来社外秘であるからです。その詳細の規定は、志望者が正式に入社するまで渡す義務がないためです。
そして当然給与体系も人事評価システムも企業ごとで大きく違います。
したがって、実際にその企業に入社する前にその企業の給与体系も人事評価システムの情報を得るためには、親しい先輩に取材するか、就活・転職口コミサイトの給与や評価に関する口コミを探しまくってイメージをつかむしかありません。
ある程度志望したい企業が決まったら調べてみるべきですが、この記事では一般的に企業の給与体系はどうなっているのかの概要を解説します。
就活を進める上での基礎知識として役立ててください。
給与体系の種類
殆どの企業が「年功序列主義」、「成果主義」の2つの基本的な考え方を基に、各企業独自の細分化やウェイト、傾斜(カーブ)を設定して給与体系をつくっています。
一つずつ概要を説明していきます。
年功序列主義の給与体系
年功序列主義の給与体系は日本独特の給与体系です。
就活をしている皆さんなら、年功序列主義と終身雇用システムは戦後日本企業の発展を支えてきたものとして、概要は理解していると思います。
年功序列とは、勤続年数や年齢という要素を重視する給与体系です。もちろん単純に年齢や社歴が古くなれば給与や役職が上がっていくというものではありません。
実際には純粋な年功序列という体系ではなく「年功序列をベースにした給与体系」となります。
年功序列をベースにした給与体系には、まず年齢を基準とした年齢給というものが存在します。
年齢によって給与の基礎になる金額が設定してあり、年齢が上がるほど少しずつ額が上がっていきます。(ただし年齢給の上限がある年齢(例:50歳・55歳など企業によって差がある)によって決められ、それ以降は同額か若干下がっていくのが一般的です)
年齢給表の例
| 年齢 | 年齢給 |
| 18 | 70,000 |
| 19 | 72,500 |
| 20 | 75,000 |
| 21 | 77,500 |
| 22 | 80,000 |
| 23 | 82,500 |
| 24 | 85,000 |
| 25 | 87,500 |
| 26 | 90,000 |
| 27 | 92,500 |
| 28 | 95,000 |
| 29 | 97,500 |
| 30 | 100,000 |
| 31 | 102,500 |
| 32 | 105,000 |
| 33 | 107,500 |
| 34 | 110,000 |
| 35 | 112,500 |
| ~ | |
| 50 | 136,000 |
| 51 | 136,000 |
| ~ | |
| 60 | 136,000 |
この年齢給とは別に「職能給」があり、職能給は縦軸に号棒、横軸に等級が設定してあります。
縦横のマトリックスにあてはまる金額が設定された表と理解してください。呼び方は企業により「職能給」や「能力給」等の違いがあります。
職能給表の例
| 号棒 | 1級職 | 2級職 | 3級職 | 4級職 | 5級職 | 6級職 | 7級職 |
| 1 | 90,000 | 110,000 | 134,000 | 171,500 | 221,500 | 287,500 | 362,500 |
| 2 | 91,000 | 111,200 | 135,500 | 173,500 | 223,700 | 290,000 | 365,000 |
| 3 | 92,000 | 112,400 | 137,000 | 175,500 | 225,900 | 292,500 | 367,500 |
| 4 | 93,000 | 113,600 | 138,500 | 177,500 | 228,100 | 295,000 | 370,000 |
| 5 | 94,000 | 114,800 | 140,000 | 179,500 | 230,300 | 297,500 | 372,500 |
| 6 | 95,000 | 116,000 | 141,500 | 181,500 | 232,500 | 300,000 | 375,000 |
| 7 | 96,000 | 117,200 | 143,000 | 183,500 | 234,700 | 302,500 | 377,500 |
| 8 | 97,000 | 118,400 | 144,500 | 185,500 | 236,900 | 305,000 | 380,000 |
| 9 | 98,000 | 119,600 | 146,000 | 187,500 | 239,100 | 307,500 | 382,500 |
| 10 | 99,000 | 120,800 | 147,500 | 189,500 | 241,300 | 310,000 | 385,000 |
| 11 | 100,000 | 122,000 | 149,000 | 191,500 | 243,500 | 312,500 | 387,500 |
| 12 | 101,000 | 123,200 | 150,500 | 193,500 | 245,700 | 315,000 | 390,000 |
| 13 | 102,000 | 124,400 | 152,000 | 195,500 | 247,900 | 317,500 | 392,500 |
| 14 | 103,000 | 125,600 | 153,500 | 197,500 | 250,100 | 320,000 | 395,000 |
| 15 | 104,000 | 126,800 | 155,000 | 199,500 | 252,300 | 322,500 | 397,500 |
| 16 | 105,000 | 128,000 | 156,500 | 201,500 | 254,500 | 325,000 | 400,000 |
| 17 | 106,000 | 129,200 | 158,000 | 203,500 | 256,700 | 327,500 | 402,500 |
| 18 | 107,000 | 130,400 | 159,500 | 205,500 | 258,900 | 330,000 | 405,000 |
| 19 | 108,000 | 131,600 | 161,000 | 207,500 | 261,100 | 332,500 | 407,500 |
| 20 | 109,000 | 132,800 | 162,500 | 209,500 | 263,300 | 335,000 | 410,000 |
| ~ | |||||||
| 30 | 119,000 | 144,800 | 177,500 | 229,500 | 285,300 | 360,000 | 435,000 |
| ~ | |||||||
| 40 | 129,000 | 156,800 | 192,500 | 249,500 | 307,300 | 385,000 | 460,000 |
| ~ | |||||||
| 45 | 134,000 | 162,800 | 200,000 | 259,500 | 318,300 | 397,500 | 472,500 |
「等級」は昇進によって上がり、「号俸」は在職年数や年間の評価によって上下するのが一般的です。
「等級」を上げる昇進は、役職がない所謂「平社員」から「主任」、「係長」、「課長代理」、「課長」、「次長」、「部長代理」、「部長」~等の人事制度上のランクの序列を表現するものと考えれば分かり易いでしょう。
ただし、等級は対外的な役職名と一致するわけではありません。職能給表は社外向け、社内向けの役職名称ではなく、1,2,3、またはA,B,C,などの等級名で管理されているのが一般的です。たとえば主任と係長は同じ等級、課長代理と課長は同じ等級になる場合のように役職上の階段と必ずしも連動はしません。
等級は総合職、現業職、一般事務職などの職制や職種によって区分して運用している企業が一般的です。例えば同じ22歳の大卒新卒で入社しても、一般職は1級職、総合職は3級職となりスタート時点から使用するテーブルが違う場合がほとんどです。
企業によっては更に細かい職種別に職能給表を設定して運用しています。
その場合は職制の違いで同じ役職でも当てはめる等級と号棒が違ってきます。縦軸の号棒による昇給の幅にも差があります。結果的に、例えば営業部長と総務部長では、同じ部長でも給与に差が出ることになるのです。
縦軸の号棒の運用方法は企業によって差がありますが、一般的には在職年数や人事考課によってより優れた成績を上げたと判断した場合は高い号棒を当てはめ、昇給額を決めるものと考えれば分かり易いと思います。
この年齢給と職能給を併せて「基本給」としている企業が多いのです。
多くの企業が等級号俸制の賃金表をベースにして、昇進(等級のアップ)と、昇格(号俸のアップ)によって給与額(基本給)を決めています。
職区分により給与の差が出る一番の理由
職制区分ごとに昇格、昇進のスピードの違いや昇進の限界があるのが一般的です。
たとえば一般職の社員が10年勤めた場合、号棒のアップで給与は上がっても、昇進(等級のアップ)が遅い(あるいは出来ない)ために役付きとなれないという事象が起こります。
その結果給与の上昇が総合職で10年勤めた社員と差が出るということになります。
また役付きになれば、基本給にプラスして役職給がついたり、管理職の別賃金体系に移行して差がついていくのが年功序列の給与体系の特徴です。
この運用上の昇進スピードと等級の限界が、総合職、エリア総合職、一般職にあるのが実情です。
従って「高い給与を獲得できる可能性の高さ」を考えれば総合職が最も有利な選択になります。
しかし、日本企業も昔ながらの表をそのまま使用している訳ではありません。
基本の考え方は残しつつも等級や号棒、金額や運用方法の調整を行いながら、全体的に公平性が保てるように(社歴によって大きな不公平が生じないように)修正しながら運用しているのが実情です。
成果主義の給与体系
成果主義とは仕事の成果に対し報酬を払うという考え方です。
最も極端な例は完全歩合制(フルコミッション制)ということになりますが、労働基準法では労働者に対する賃金保障について定められているため、一般的な雇用契約の下でフルコミッション制を導入できません。
従って、社員(労働者)であれば、何らかの基本給にプラスして、成果に基づくインセンティブ(目標に対する達成度合い)によって給与の額が変動する労働契約となります。
インセンティブの設定の仕方は業界、企業によって大きく違います。保険、証券、不動産の営業はこの体系を使用している企業が多いです。
この売上や契約件数を基本にしたインセンティブ以外の成果主義も存在します。
職務給の導入
外資系企業(日系企業でも一部新興企業やベンチャー企業含む)の多くは、JOB PROFILE(職務)を詳細に規定し、その職務を遂行すること、設定された指標の達成度合い(レベル)によって年収を合意するという給与体系をとっています。
それに加え、その期の業績が良ければ決算後にそれに応じたボーナスが加算されるというシステムです。悪ければボーナスの加算はありません。基本的には仕事の内容(達成レベル)と年収を企業と労働者で「握る=合意する」という考え方です。
この成果主義の給与体系を一言で表すと「仕事に人をつける」ということになります。
職務給においては業務の種類に基づいて賃金が決定されるため、成果や責任に応じて給与は変わります。
年齢や職能給のように勤続年数に関係なく、JOB PROFILEに応じた働きによって賃金や昇進の評価を行う方式となります。
日本企業の場合日本的な雇用形態である年功序列のコンセプトを一部残し、職務給を導入する企業も増えてきました。
ある一定の役職までは年齢給と職能給という年功序列の体系を残し、それ以上の管理職になった場合は成果主義を反映した職務給に切り替えるなどのやり方です。
あるいは年収を基本としますが敢えて日本の慣行を踏まえて、年収を給与12ヵ月と賞与2回に分け、賞与に関しては業績連動を行なって、業績が良い場合は加算する等のやり方をとっています。
融合、アレンジの仕方は企業の考え方や業界、ポジショニングによって様々なので外からでは分かり難く、入社してみないと分からないというのが実情です。
給与以外の手当てについて
企業が社員(労働者)に支払うのは給与のみではありません。
具体的には、残業手当、通勤手当(定期代・ガソリン代)、住宅手当(家賃補助)、家族手当、(管理職になった時の)管理職手当、などの各種手当がありますが、これらの手当ての有無、支給条件、支給額とも個々の企業によって全く異なるので注意が必要です。
残業代の設定や計算方法も企業によって異なります。毎月〇〇時間以内の残業は基本給に含まれるという設定で、〇〇時間以上の残業から手当の支給対象になる場合や、残業手当に上限を設けている企業など、手当の付け方は様々です。
残業手当や通勤手当以外の手当ては、有無も含めて企業によって大きな差があります。
たとえば家賃補助の有無・額の高低は、結婚後のQOLに大きな影響を及ぼすファクターです。
あくまで一般論ですが、世間的に誰しもが知っている大企業で、且つ歴史のある企業は家賃補助制度や、金銭以外の福利厚生が充実してい傾向が強いのも事実です。
各種手当に関しては内定獲得以前に知る方法は親しい先輩に取材するか、口コミを拾い集めてみるしかありません。また社員の給与明細を集めて公開しているWEBサイトもあるので、捕捉・チエック用として利用してみる手はあります。
心配であれば応募要項に出ている初任給の構成は適切な時に人事担当に聞いてみるも良いと思います。
給与から控除されるもの
基本給に手当をプラスしたものが給与支給総額であり、そこから各種控除を引いたものが差引支給額(手取)金額となります。
念のためですが、応募要項にでている初任給の額は手取り金額ではありません。
支給総額から引かれる控除には以下のものがあります。
- 健康保険
- 介護保険(40歳から)
- 厚生年金
- 雇用保険
- 所得税
- 住民税
これらの保険や税の控除は必要なものとは言えかなりの額(入社初年度であれば年収の2割程度)にのぼるので、就職後の生活設計もしっかりイメージしておきましょう。
まとめ
どういう給与体系が優れているかは一概に言えません。それぞれ一長一短があり、また業態や仕事の内容に合う、合わない、社員の価値観も違うため一般論で括ることはできません。
ある程度「興味が持てる業界」、「やりたい仕事」が見えてきたら、企業研究をして志望したい企業の応募職種や給与に関する情報を探っていきましょう。
はじめは初任給や、30歳到達時の年収、平均年収を同業界で少なくも5社ほど調べれば、だいたいのイメージはつかめると思います。
それ以上気になればOB/OG訪問や先輩のつてや、Web上の口コミ情報を探ってみてください。
給与の高さや福利厚生の充実度は、仕事のモチベーションにも大きな影響を与えるファクターです。後で後悔しないように、きっちりチェックしていきましょう。
就活のスタートには、自己分析のサポートツールで自分の強みを発見しよう
「自己分析」は就活のイロハの「イ」ですが、時間がかかり大変です。そして自分を冷静に見つめ直すのも難しいものです。
そんな時、力になるのは本格的な適職診断ソフト、「Analyze U+」です。
「Analyze U+」は251問の質問に答える本格的な診断テストで、質問に答えていくと経済産業省が作った「社会人基礎力」を基に、25項目に分けてあなたの強みを偏差値的に解析してくれるものです。
本当のあなたの強みや向いている仕事を素早く「見える化」してくれます。
「Analyze U+」を利用するには、スカウト型就活サイト「OfferBox![]() 」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
OfferBox![]() は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
手早く自己分析を済ませ、就活の流れに乗っていきましょう。