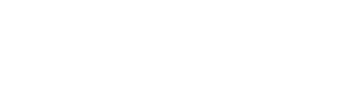この記事は障がいのある学生が、就活に向かうにあたり知っておくべき基礎的なことを解説しています。
障がいのない学生や、「障がいがあるかもしれない」と考えている方も、社会人となって多様性を尊重し、共生社会を一緒に生きていく仲間として知っておいてほしい情報です。
筆者は同じ職場で働いている同僚や部下が、ストレスや過労で精神的にも肉体的にも追いつめられて長期休養の末に退職していった事例を何人か見てきました。
またクライアントの若手社員が、スキーで障害を負ってしまいクライアントの職場に復帰できなかったか例もありました。
人の一生には何が起こるかは分からないものです。そして誰もが生きていくために、周囲の人々や社会からのサポートが必要です。
障がいのある人はそのサポートがより必要なだけで、本質的に同じです。そして障がいのある方が、働きやすい会社はそれ以外の方にとっても働きやすい職場と言えるでしょう。
自分の状態や価値観に合った企業に就職したいと考えることも、一般の就活生と同じです。
従って「就活の答え」で解説している様々な就活ノウハウの本質的な部分は、障がいのある学生にも参考にして欲しいと考えています。
この記事では、それ以外で知っておくべき基本的なことを解説していきます。
Contents
自分に正直に向き合う自己分析から始めよう
本人だけが実感している本当の障がいの現状と、障がいによって発生する制限や配慮が必要なことと「向き合う」ことからはじめましょう。
そして自分の価値観、性格、特徴(長所・短所、強み・弱み)の分析、自己PRできる要素の抽出を経て、興味が持てる業界の研究をしていきます。
上記二つと、障がい者手帳に記載している情報(障がい名と等級)をあわせて、自分が就労可能な企業を探していくことになります。
障がい者雇用制度について知っておくべきこと
障がい者雇用制度とは
既に障がい者雇用制度をよくご存知の方は、飛ばして先に進んでください。
障がい者雇用とは、障がいのある方が社会で暮らし、活躍できるように、企業が障がい者を優先的に採用する制度であり、「障害者雇用促進法」によって定められています。
この制度の対象になるのが「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」を持っている人です。
企業や国・地方公共団体には障害者雇用促進法によって達成すべき障がい者の雇用率が以下のように定められています。
- 民間企業:2021年4月以降は0.1%引き上げられて2.3%
- *従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければならない
- 国・地方公共団体: 2021年4月以降は0.1%引き上げられて2.6%
つまり、企業や公共団体には一定数以上の障がい者を雇わなければならないというルールが定められているのです。
障がい者雇用制度の現状と課題
障がい者雇用制度の現状
就活生の皆さんの中には、中央省庁における大規模な障害者雇用者数の水増し問題が2018年にマスコミでも大きく取り上げられたことを覚えている方も多いと思います。
厚生労働省が発表している2020年6月1日現在の障がい者雇用の現状は以下の通りです。
| 雇用者数 | 対前年比 | 実雇用率 | |
| 民間企業 | 578,292人 | +3.2% | 2.15% |
| 国 | 9,336人 | +23.2% | 2.83% |
| 都道府県 | 9,699.5人 | +7.4% | 2.73% |
| 市町村 | 31,424人 | +8.4% | 2.41% |
| 教育委員会 | 14,956人 | +11.0% | 2.05% |
| 独立行政法人 | 11,759.5人 | +1.3% | 2.64% |
2020年6月1日現在では、法定雇用率達成している民間企業の割合は48.6%であり対前年比では0.6ポイントの微増と言う状況です。
微増はしているものの、全体の半数以上の企業が方手雇用率を守っていないことになります。
障がい者雇用制度の課題
法律で定められているにも拘らず、守っていない企業が多い理由は、現状の制度が法定雇用率を超えて障がい者を雇用する企業には補助金を与え、未達成の企業からは納付金を徴収するという仕組みになっているからです。
未達状態が続く企業に対しては労働局から指導が入り、それでも適正な措置を講じない企業は企業名を公表するという制度設計になっています。
この企業名公表制度によって誰もが知っているような大企業や上場企業は、コンプライアンスの遵守や社会的責任も大きいため法定雇用率を達成していますが、企業の大半を占める中小企業は障がい者を雇用したくても余裕がないため、仕方なく納付金を収めているという現状があるためです。
具体的には常用労働者の総数が100人を超える事業主は、障害者法定雇用率が未達成の場合、法定雇用障害者数に不足する障がい者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付します。
例えば常時雇用者が500人の企業であれば、法定雇用率2.2%を乗じると11人の障がい者を雇用すべきということになります。
その場合、11人の障がい者を雇用するコストと、例えば5人の障がい者を雇用して、残りの6人分の納付金を支払う費用とを比較して考え、後者を選択する企業が多いのが法定雇用率達成企業の割合が高くならない理由なのです。
逆に常時雇用労働者数が100人を超える事業主で、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万7千円の障害者雇用調整金が支払われるという制度設計になっています。
上記以外にも細かい給付金や報奨金の制度がありますが、一言で言うと「本来障がい者雇用を増やすべき中小企業に、実際の雇用を増やすインセンティブが働かない」という大きな課題があるのです。
障がい者雇用に取り組んでいる企業の考え方の差に注意しよう
障がい者雇用に積極的に取り組んでいる企業は、大企業や中小企業を問わず数多く存在します。
しかしその取り組み方には差があります。
企業名の公表という罰則を恐れて取り組んでいるという企業もありますし、障がい者も含め多様な人材が活躍できる環境を整えようと真剣に取り組んでいる企業もあります。
障がい者の雇用を作る、雇用を確保するという意味では現状の制度が機能していることは確かですが、それぞれの障がい者が望んでいる雇用の形態や仕事として実現できているかは別です。
「特例子会社」による採用と仕事
現状の法制度では、「特例子会社」と「グループ適用」という障がい者雇用の雇用率を達成するための「裏技」があります。
特例子会社:
- 障がい者の雇用の促進・安定のため、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できる仕組み
グループ適用:
- 上記の特例子会社を持つ親会社は、関係する子会社も含め、企業グループによる実雇用率算定が可能になる仕組み(障がい者雇用法定雇用率をグループとして達成していれば良い)
具体的には、親会社や関係する子会社に存在する障がい者ができるような作業を集約して、それを行うための子会社を設立し、その特例子会社で障がい者を雇用するというカタチになります。
親会社や関係子会社がその特例子会社に委託する業務は、親会社の判断によって差が出ますが、一般的に「障がい者ができるような作業」とは清掃や制服のクリーニング、郵便物の社内仕分、シュレッダーをかける等の作業が中心になります。
働く障がい者からの視点では、親会社や関係子会社に所属して働いているという意識と現実のギャップが生まれる可能性もあるため、就活に際してはしっかりと雇用形態や仕事の内容を把握しておきましょう。
もちろん上記のような軽作業を歓迎する方も多いため、障害の現状や自分の価値観との見合いが必要になるのです。
障がい者雇用を引き受ける企業における仕事
近年、企業から障がい者雇用を専門に引き受ける企業がでてきました。
その仕組みを説明すると以下のようになります。
- 障がい者は企業Aに志望し、企業Aはその障がい者に内定を出し、採用する⇒
- 障がい者雇用を専門に引き受ける企業Bは自ら運営する農園(の一部)を企業Aに貸し出し、企業Aは障がい者をその農園に送る⇒
- つまり、障がい者の実際の職場は企業Aではなく、企業Bが運営する農園となる⇒
- 企業Bの農園(企業Aに貸し出された農園)で収穫された農作物は企業Aの社員食堂で使用、社内販売で社員に販売する、もしくは福利厚生の一環として社員に配られる
この場合でも障がい者は企業Aの社員という身分は保証され、企業Aはその障がい者を自社の障がい者雇用にカウントできます。
しかし障がい者の視点からは、企業Aに所属し、企業Aに「貢献して、その対価を得る」という意識とのギャップが更に大きくなることもあるでしょう。
上記の特例子会社以上に、雇用形態や仕事の内容を事前にチェックする必要がある事例です。
障がい者が行う就活の方法論
障がい者雇用の現状と課題を理解した上で、実際に行う就活のルートは大きく、以下の三つのルートに分かれます。
- 障がい者であっても障がい者手帳を使わず(障がい者であることを公開せず)一般採用枠での就活をすすめる
- 障がい者手帳を使って、障がい者雇用枠での就活を進める
- 志望する企業によって障がい者手帳を使っての障がい者雇用枠での就活と、障がい者手帳を使わず(障がい者であることを公開せず)一般採用枠での就活を併用する
どのルートを選ぶかは障がい者の障がいの現状や価値観にもよると思います。
障がい者手帳を使わずに進める就活とは?
ここで「障がい者であることを公開せず、就職活動を進めても良いのか?」という疑問を持つと思います。
障害者雇用促進法の第34条では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」としており、障がい者であることを公開しなくても就職活動を行なうことができます。
また第35条では、「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない」と規定しています。
しかし、「障がい者であることを公開せず、就職活動を進める」ということは、一般採用ルートでの就活となることを意味します。
当然、将来行える仕事の可能性は大きく広がるというメリットがあります。
しかし選考は他の就活生と全く同じ土俵で評価されることになり、内定を獲得して入社した場合は障がいを配慮してもらう権利、合理的な配慮を放棄するということになります。
障がいの度合いによってこのルートを選択するかどうかの判断は分かれると思います。
このルートを選択し、内定を獲得、入社した場合、仕事の成果として求められるものは一般社員と全く同じとなります。
そのため入社後、障がいの程度と仕事の困難性の間で苦しむことになる可能性もあり、注意が必要です。
障がい者手帳を使う、障がい者雇用枠での就活
企業の採用ページを検索すると、障がい者採用のページを設けている企業もあるので、まず2~3社を「企業名+障がい者採用」で検索してチェックしてみましょう。
障がい者雇用の枠でエントリーし、無事内定を獲得して入社が決まると、入社時に自分の障がいや病気などに対する配慮(合理的配慮)を求めることができます。
通院や入院が必要な場合休みや遅刻・早退を取得できる、仕事をする上で必要なツールや機器、設備等を準備してもらえる、といった、障がい者の持つ障がいに合わせた職場環境を企業側が配慮し提供してくれるという大きなメリットがあるのです。
デメリットとしては、障がい者雇用枠での募集職種は事務職や軽作業などの職種が多いことです。従って総合職のように仕事の可能性を広げることが難しいという制約があります。
自分の可能性を伸ばしたい、チャレンジしたいという方に合う仕事や職場に出会うことが難しいのが実情です。
前述の「特例子会社」に入社の場合は、親会社の給与や待遇ではなく特例子会社の規定によって決まるため、親会社と差がでることもあります。
併用という第三の道
就活に際して、上記の2つのルートを併用することも可能です。
障がいの度合いと自分のやりたいこと、チャレンジしたいことによってこのルートを選択するかどうかの判断は分かれると思います。
それぞれのルートのメリット、デメリットと企業や仕事の魅力度の間で悩むことになるかと思いますが、一般ルートでも「いけるかも」と思ったら負担を考慮しながらチャレンジしてみるのも良いかと思います。
一般ルートでの就活は過酷ですが、どんな結果になるにせよ「チャレンジした結果」としての納得感は得られるでしょう。
プロのアドバイスを活用しよう
現在の就活はやることや準備することも多く、学生にとっては大きな負担を強いるカタチになってしまっています。
一般の学生以上に考えなければならないポイントが多いのが障がい者の就活です。
障がい者の就活は、まず一番身近な大学のキャリアセンターに相談してみましょう。
そして障がい者専用ナビへの登録や、障がい者専門就活エージェントを活用するなど、あなたをサポートしてくれる人や組織があることが分かれば展望も開けてきます。
心配するよりまず行動です。
大学のキャリアセンターに個別の相談を申し込んで、しっかりとしたガイダンスをまず受けましょう。
またマイナビ 2023チャレンジドという障がいがある学生に特化したナビサイトもあります。このサイトでは大卒新卒の障がい者向け求人を探すことができ、就職準備講座や説明会・イベントの開催もしています。ぜひ「7マイナビ 2023チャレンジド」で検索してみて下さい。
そして、さらに心強い存在なのが障がい者を専門にサポートしてくれる人材エージェントの存在です。
いままでは転職を中心にしたサービスを行っている企業が大半でしたが、新卒の就活生に寄り添って並走してくれるエージェントも数社存在します。
一人で悩まずに、無料で受けられるサービスを上手に使って自分にベストな「就活の答え」をみつけていきましょう。
就活のスタートには、自己分析のサポートツールで自分の強みを発見しよう
「自己分析」は就活のイロハの「イ」ですが、時間がかかり大変です。そして自分を冷静に見つめ直すのも難しいものです。
そんな時、力になるのは本格的な適職診断ソフト、「Analyze U+」です。
「Analyze U+」は251問の質問に答える本格的な診断テストで、質問に答えていくと経済産業省が作った「社会人基礎力」を基に、25項目に分けてあなたの強みを偏差値的に解析してくれるものです。
本当のあなたの強みや向いている仕事を素早く「見える化」してくれます。
「AnalyzeU+」を利用するには、スカウト型就活サイト「OfferBox![]() 」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
OfferBox![]() は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、登録して損はありません。
手早く自己分析を済ませ、就活の流れに乗っていきましょう。
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します