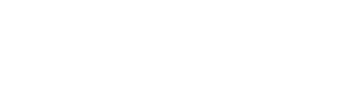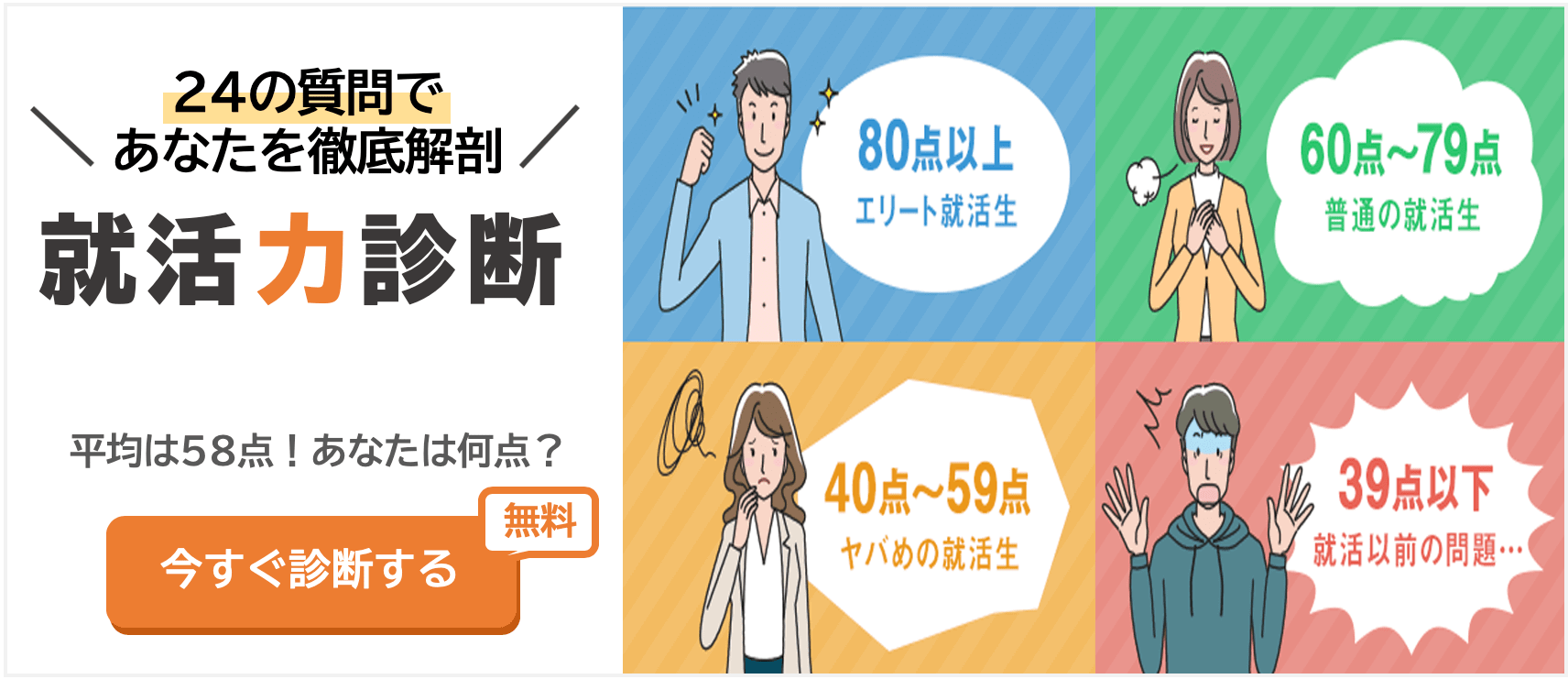就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するためのコンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。
飲料業界情報の7つのポイントを押さえよう
- 飲料業界のビジネスモデルを理解しよう
- 飲料メーカーの現状と課題・未来
- 飲料メーカーにはどんな仕事があるのか、職種の情報
- 飲料メーカーで働く人のモチベ―ションは何か
- 飲料メーカーに向く人、向かない人はどんな人か
- 飲料業界の構造
- 主要飲料メーカーの概要
この記事では飲料業界の構造と、業界の主要企業の概要や業績が短時間で理解できるようにまとめました。就活の業界研究の一助として活用してください。
Contents
飲料業界の構造
清涼飲料水市場

まず清涼飲料水市場の構造をみていきましょう。
2022年度の清涼飲料市場は、前年2021年度比6.8%増の4兆1,537億円(2021年度は3兆8,909億円)*の市場規模なっています。(*販売金額、全国清涼飲料連合会)
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で2019年比7.3%減に落ち込んだところこら、2021年度、2021年度と回復してきました。
2022年度の清涼飲料水全体の販売金額は、コロナの影響がなかった2019年度(4兆985億)を上回る結果となっています。
同じく一般社団法人 全国清涼飲料連合会のデータの、2022年における容器別の構成比(生産数量ベース)ではPETが78.2%を占め、缶10.1%、紙容器7.5%、びん0.9%、その他容器(パウチ、チルドカップ等が3.3%になっています。
PETボトルの容量別の構成比でみると、400ml~699mlが68.3%を占め、大型700ml 以上が26.1%、小型(1-399ml)が5.5%という割合でした。
実際には消費者のライフスタイルや価値観の多様化に合わせて、各社は細かく容器/容量のSKUを増やす傾向となっています。
2022年の飲料別構成比は、生産ベースでみると、シェアの高い順で、お茶飲料が最も多く24.6%、ミネラルウォーター19.6%、炭酸飲料16.7%、コーヒー飲料が13.3%、果実飲料6.5%、スポーツ飲料6.1%、紅茶飲料4.6%、その他飲料(野菜飲料・豆乳飲料等)8.5%という割合でした。(出典:全国清涼飲料連合会)
2020年における品目別販売金額シェアをみると、シェアの高い順で、コーヒー飲料20.0%、茶系飲料19.6%、炭酸飲料18.6%、ミネラルウォーター類8.9%、スポーツ飲料8.1%、果実飲料8.1%、紅茶飲料5.2%、その他の飲料(野菜飲料・豆乳飲料等)11.5%となっています。
メーカー別のシェア(飲料メーカー上位10社の売上高ベース 2021-2022年:出典:業界動向SEARCH.COM)では、サントリーホールディングスが29.8%、コカコーラボトラーズ18.6%、ヤクルト本社9.8%、大塚ホールディングス9.6%、伊藤園9.5%、アサヒグループホールディングス8.3%、キリンホールディングス5.8%と続いていきます。
以下、ダイドーグループホールディングスドリンコ、サッポロホールディングス、カゴメ、となっており、ここまでの10社でマーケットのほとんどを占める寡占、且つ非常に競争が激しいことが分かるデータです。
酒類市場

次に、令和3年度(2021/4/1-2022/3/31)おける酒税収入の内訳では、3割超がビール(約3,862億円:34.0%)であり、発泡酒(約803億円:7.1%)や、チューハイ・新ジャンルが大部分を占めるリキュール(約2,481億円:21.9%)を合わせると、これら低アルコール飲料が全体の約3分の2を占めていることが分かります。
焼酎は甲類・乙類をあわせて14.8%、スピリッツ等7.5%、ウィスキー5.1%、清酒・合成酒はあわせて3.7%、その他6.0%という順になっています。(データ:国税庁:酒税収入の状況)
あくまで消費量ベースですが、国内酒類市場を俯瞰してみると、ビール、発泡酒、第三・第四のビール、チューハイの市場を制することの重要性を直感的に分かってもらえると思います。
酒類全体を長期トレンドでみると、課税数量がピークであった平成11年度(1999年)には1,017 万Klから、令和3年度(2021年)には799万Klという結果であり、ピーク時の約8割弱(78.6%)の水準になっています。
課税数量の落ち込みは、新型コロナウイルス感染症拡大が始まった年の令和2年度(2020年)から激しくなり、令和3年(2021年)になっても減少傾向が続きました。
行動制限が緩和・撤廃された現在は回復期にありますが、酒類の消費量は長期的に減少傾向が続くことが予測されています。
ピーク時の平成11年度から現在の間は、特にビールの課税移出量が大きく減少し、ビールからチューハイやビールに類似した新ジャンル飲料(カテゴリーとしてはリキュール類)へ移行(置き換わり)をしているのが大きな特徴です。
2023年10月から第3のビールに対する酒税が引き上げられ、ビールは引き下げられる改正があり、発泡酒や新ジャンルとの価格が縮まるため、今後はビールの消費が伸びることが予測されています。
- 2023年10月からはビールにかかっている酒税が現在の70円から63.35円となり、6.65円の減税
- 発泡酒は46.99円のまま据え置き
- 第3のビールは37.8円から46.99円に引き上げられる
酒類・飲料メーカーを志望する皆さんは、酒税に関するニュースにも敏感になっておきましょう。
ビール類のメーカー別シェア(参考):
2022年のビール類(ビール、発泡酒、第3のビール)メーカー別シェア(市場占有率)でみると、4社の販売数量を基にシェアを計算するとアサヒが36.5%、キリンが35.7%、サントリーが16.2%、サッポロが11.6%と推計されています。(データ引用:2023年1月 14日 ダイヤモンド オンライン調べ)
2020年よりキリンビールが第3のビールである「本麒麟」の大ヒットによって、トップシェアをアサヒビールから首位を奪還していましたが、2022年では再びアサヒが首位に返り咲いたカタチです。
コロナ禍では業務用需要が大幅に減り、飲食店で約半数が売れていたビールが全体で22%も減少した一方、主に家庭で消費される第3のビールは3%増加していましたが、行動規制の緩和によってビール需要の改善傾向がみられたことや、アサヒビールの新製品のヒットが寄与したことが寄与しています。
製品・ブランドの新発売や改変期の影響や税制の変更という要因もありますが、酒税の動向や、With/Afterコロナの社会情勢を注意深くモニターしていきましょう。
飲料業界大手メーカーの概況
このように飲料業界は寡占市場のため、飲料大手の概況を知っておくことは飲料業界への就活には非常に重要です。
以下、主要各社の中期経営計画や有価証券報告書を中心に分析していますが、各社を志望する方は、ぜひそれらの情報をご自身で深堀して研究を進めて下さい。
自分は飲料業界に向いているタイプか、適性を診断してみよう
自分の適性や性格が、飲料業界の仕事に向いているのかどうか、気になりませんか?
そんな時、力になるのは本格的な適職診断ソフト、「Analyze U+」です。
「Analyze U+」は251問の質問に答える本格的な診断テストで、質問に答えていくと経済産業省が作った「社会人基礎力」を基に、25項目に分けてあなたの強みを偏差値的に解析してくれるものです。
本当のあなたの強みや向いている仕事を素早く「見える化」してくれます。
「AnalyzeU+」を利用するには、スカウト型就活サイト「OfferBox![]() 」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
OfferBox![]() は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、就活で納得のいく結果が得られるかどうかに不安を抱いている人、自己分析がうまくいかない人や選考がうまくいかない人でも登録しておくのがおススメです。
は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので、就活で納得のいく結果が得られるかどうかに不安を抱いている人、自己分析がうまくいかない人や選考がうまくいかない人でも登録しておくのがおススメです。
手早く本格的で客観的な自己分析を済ませ、納得の結果を追求していきましょう。
サントリーホールディングス株式会社
2022年12月期連結決算(2022年度)
| 売上収益:酒税込み (百万円) | 2,970,138 |
| 売上収益:酒税控除後 (百万円 | 2,658,781 |
| 税引前利益(百万円) | 261,818 |
| 当期利益 (百万円) | 188,533 |
| 親会社株主に帰属する当期利益(百万円) | 136,211 |
| 当期包括利益(百万円) | 511,177 |
| 従業員数(人) | 40,885 |
| 外、平均臨時雇用者数 | 6,779 |
| 子会社 | 235社 |
| 持分法適用関連会社 | 34社 |
サントリーホールディングスの事業セグメント概要
サントリーは「飲料・食品」と「酒類」の2つのコア事業をグローバルに展開し、持株会社、親会社、子会社235社、持分法適用会社34社により、飲料・食品・酒類の製造、販売、その他の事業活動を行っている巨大企業です。その他の中には健康食品・化粧品事業やハーゲンダッツ事業等を含みます。
飲料・食品セグメント:
- 飲料・食品セグメントの事業は、サントリー食品インターナショナル株式会社及びその子会社により、日本、欧州、アジア、オセアニア、米州等で、清涼飲料水の製造・販売を行ない、サントリーフーズが国内の流通・小売企業に販売を行う体制です。
- またサントリービバレッジソリューション株式会社が自動販売機事業と飲食店向けのディスペンサーによる販売(ファウンテン事業)を主に行っています。
- 上記以外にも、ジャパンビバレッジホールディングスが自動販売機を通じた清涼飲料水の販売をしており、加えてサントリープロダクツが清涼飲料品の製造を受託しています。
- 国内のみならず、海外でも地域・国ごとの海外子会社で清涼飲料水の製造・販売を行う構造です。
酒類セグメント:
- スピリッツ類に関してはサントリー株式会社*のスピリッツカンパニー及びBeam Suntory Inc.とその子会社が米国及び世界の様々なエリアでスピリッツの製造・販売を行なう体制となっています。
- 2022年7月1日付で、サントリースピリッツ(株)を吸収合併存続会社、サントリーBWS(株)・サントリービール(株)・サントリーワインインターナショナル(株)及びサントリー酒類(株)をそれぞれ吸収合併消滅会社とする吸収合併を実施し、吸収合併後、サントリー株式会社に商号を変更しています。
- スピリッツ以外の種類に関しても、サントリー株式会社において、ビール類はビールカンパニー、ワイン類はワインカンパニー、酒類販売をセールスマーケティングカンパニー行う体制に再編しています。
その他のセグメントには、健康補助食品、特定保健用食品、栄養機能食品(サントリーウェルネスによる)やハーゲンダッツジャパンによるアイスクリームの製造・販売事業、外食事業(ダイナックスホールディングス)や花苗・切花事業(サントリーフラワーズ)や中国事業(サントリー(中国)ホールディングス)の事業が含まれています。
2022年12月期(2022年度)連結決算の概要
2022年12月期におけるサントリーホールディングスの連結業績は、売上収益(酒税込み)が2兆9,701億円(前年同期比、以下同116%)、売上収益(酒税控除後)2兆6,588億円(同116%)、売上総利益1兆1,907億円(同111%)となっています。
利益面では、当期利益が1,885億円(同121%)となり、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,362億円(同120%)となり、総じて増収・増益を達成した年度となっています。
ちなみに、2022年度の売上収益、当期利益共に、コロナの影響が全くなかった2019年1月期(2019年度)を超える業績となっています。
2022年12月期年の飲料・食品、酒類、その他のセグメント別業績概要は以下の通りです。
2022年12月期 セグメント別業績概要
| 事業名 | 外部顧客売上収益(百万円)酒税控除後 | 売上構成比 | セグメント利益 (百万円) |
利益構成比 |
| 飲料・食品セグメント | 1,444,852 | 54.3% | 162,079 | 49.2% |
| 酒類セグメント(酒税控除後) | 935,598 | 35.2% | 140,627 | 42.7% |
| その他セグメント | 278,331 | 10.5% | 26,990 | 8.2% |
| 合計 | 2,658,781 | 100.0% | 329,696 | 100.0% |
| 調整額(全社管理費用等)* | ー | ー | -53,228 | ー |
| 計上額 | 2,658,781 | ー | 276,468 | ー |
*セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれています
セグメントごとの業績を、2021年度対比でみると、以下のような状況です。
- 飲料・食品セグメント:
- 売上収益1兆4,449億円(前年同期比、以下同114%)、営業利益1,621億円(同116%)
- 飲料・食品セグメント:
- 売上収益(酒税込み)1兆2,459億円(同118%)、売上収益(酒税控除後)9,356億円(同119%)、営業利益1,406億円(前年同期比110%)
- その他セグメント:
- 売上収益(酒税込み)2,794億円(前年同期比117%)、売上収益(酒税控除後)2,783億円(前年同期比118%)、営業利益270億円(前年同期比106%)
サントリーホールディングスの事業の特徴
飲料・食品、酒類、両事業の特徴は、成長のために海外事業を重視している点です。2022年度におけるサントリーホールディングスの連結売上高の51%が海外売上(酒税控除後の外部顧客売上)となっています。
サントリーホールディングスは2014年、ジムビーム(バーボン)で有名な米国ビーム社を買収し完全子会社にしました。
この買収により、ビーム社とサントリーのスピリッツ事業をあわせた売上高は、43億ドルを超え、世界のプレミアムスピリッツ市場において第3位のポジションを築いたのです。その後Beam Suntory 社は着実に成長を遂げて酒類セグメントの利益にも大きく貢献しています。
コア事業の一翼を担い、飲料・食品事業のサントリー食品インターナショナルでは、2030年に売上高2.5兆円を目指す野心的な長期及び中期経営戦略を発表しています。
サントリー食品インターナショナルでは2009年フランスのオランジーナ・シュウェップスを回収して日本でも大ヒットさせるなどの成功事例もあり、今後もナチュラル&ヘルシー飲料を核に日本、欧州、アジアを中心にグローバルに事業を拡大していく計画です。
飲料食品セグメントの現在注力している課題は以下の通りです。
- コアブランドイノベーションを加速
- 売上収益の伸長及びサプライチェーンのコスト削減活動の徹底により、利益体質の改善を目指す
- 日本では、「コアブランドの成長加速」、「自販機事業構造改革」、「サプライチェーン構造革新」が事業戦略の重点領域
- アジアパシフィック・欧州では、コアブランドイノベーションやコスト削減活動の徹底等により更なるコスト増の吸収に取り組む
- 米州では、主力である炭酸カテゴリーの強化を進めるとともに、伸長する非炭酸カテゴリーの更なる拡大に取り組む
酒類セグメントの現在注力中の課題は以下の通りです。
- スピリッツ事業:
- 世界のプレミアムスピリッツのリーダーとして、プレミアムブランドの育成により、販売数量の伸長を上回る売上成長を目指す
- ビール事業:
- 事業の中核となる既存ブランドのバリューアップ、「ビアボール」の定着化、更なる新価値提案等により、新たな飲用需要を創造し、ビール類総市場の活性化を図る
- ワイン事業:
- ワイン事業は、お客様とワインの距離をより近づけ市場を活性化させる取組みを強化
サントリーには「人と自然と響きあう」という企業理念や、創業以来受け継がれている「やってみなはれ」精神、「利益三分主義」など独特の価値観、行動原理や企業文化を持っている企業です。
サステナビリティに関しても、気候変動による、水資源への影響、資源の枯渇等により、製品の安定供給及び生産コストの増加等の影響があるため、気候変動関連課題をサントリーグループのビジネスの継続の上で重要な課題の一つと認識し、気候変動の緩和を目指す政府や地方自治体の環境への取組みと連携し、バリューチェーン全体での環境負荷低減を目指し、グループ一体となって気候変動関連課題に取り組んでいます。
就活でサントリーグループを志望する皆さんは、各社の企業研究による役割や事業の理解は当然として、グループの戦略や創業以来受け継がれている企業文化を十分理解して、インターンシップ等に積極的にチャレンジしてください。
キリンホールディングス株式会社
2022年12月期連結決算(2022年度)
| 売上収益 (百万円) | 1,989,468 |
| 税引前利益 (百万円) | 191,387 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 111,007 |
| 親会社の所有者に帰属する包括利益(百万円) | 189,195 |
| 従業員数(人) | 30,538 |
| 外、平均臨時雇用者数 | 4,012 |
| 連結子会社 | 148社 |
| 持分法適用関連会社 | 30社 |
キリンホールディングスの事業セグメントの概要
キリンホールディングスはキリンビール・キリンビバレッジ・メルシャンの3社が統合して誕生した持株会社です。中核の国内総合飲料事業はこの3社を中心に展開する体制です。
- 国内ビール・スピリッツ事業:
- 麒麟麦酒株式会社が統括会社として国内のビール、発泡酒、新ジャンル、洋酒他酒類等の製造・販売を行っています。
- 国内の飲料事業:
-
- キリンビバレッジ株式会社が統括会社として、日本における清涼飲料水の製造・販売を行なう体制です。
- オセアニア酒類事業:
-
- LION PTY LTD(連結子会社)を統括会社としたオセアニア地域等におけるビール、洋酒等の製造・販売
- 医薬事業:
- 協和キリン(連結子会社:東証プライム市場上場企業)を統括会社として、医療用医薬品の製造・販売を行っています
- その他の飲料事業:
- メルシャン株式会社による、日本における酒類の輸入・製造・販売、Coca-Cola Beverages Northeast, Inc.(連結子会社)の米国におけるコカ・コーラ製品の製造・販売事業、協和発酵バイオによる医薬品原料、各種アミノ酸、健康食品の製造・販売フィリピンのビールメーカーのサンミゲルビール社(持分法適用関連会社)等の事業で構成されています。
- 株式会社ファンケル(持分法適用会社)による、日本における化粧品、健康食品の製造・販売
2022年12月期(2022年度)連結業績の概要
2022年12月期におけるキリングループホールディングの連結業績は、連結売上収益がオセアニア酒類事業、医薬事業及びコーク・ノースイースト社の増収により増加し、対前年同期比で1,679億円増加(9.2%増)して、1兆9,895億円という結果でした。
利益面では、以下の概要となっています。
- 連結事業利益:1,912億円(前年度比257億円の増益、+15.6%)
- 連結税引前利益:1,914億円(前年度比918億円の増益、+92.1%)
- 親会社の所有者に帰属する当期利益:1,110億円(前年度比512億円の増益、+85.7%)
2022年12月期におけるセグメント別業績の概要は以下の通りです。
2022年12月期 セグメント別業績概要
| 事業名 | 外部顧客売上収益(百万円) | 売上構成比 | セグメント利益 (百万円) |
利益構成比 |
| 国内ビール・スピリッツ | 663,522 | 33.4% | 74,660 | 30.5% |
| 国内飲料 | 243,257 | 12.2% | 18,786 | 7.7% |
| オセアニア酒類 | 255,900 | 12.9% | 31,545 | 12.9% |
| 医薬 | 397,863 | 20.0% | 82,462 | 33.7% |
| その他 | 428,925 | 21.6% | 37,545 | 15.3% |
| 合計 | 1,989,468 | 100.0% | 244,998 | 100.0% |
| 調整額 | ー | ー | -53,838 | ー |
| 計上額 | 1,989,468 | ー | 191,159 | ー |
キリンホールディンスの事業の特徴
キリンの特徴は清涼飲料水においても、ビール事業においてもバランスの取れたポートフォリオを組んでいる点です。会社としても三菱グループの伝統を受け継いで、組織力に強みがあります。
海外事業に関しては2011年にブラジルのビール大手、スキンカリオールの株式50.45%を約2000億円で取得しましたが、残り49.55%を保有する株主に訴訟を起こされ、最終的に全株を取得することになり買収金額は合計約3000億円に膨れ上がってしまいました。
それでも利益が出ていればよかったのですが、ブラジルの景気後退により失速してしまい、2015年12月期の連結決算はブラジルキリンを減損処理した結果、上場以来初めて560億円の赤字となってしまいました。その後、結果的に2017年に全株式を売却、撤退するという高い授業料を払う結果となりました。
逆に言えばこの失敗によって、海外展開のノウハウを蓄積できたということも言えるのです。
2021年1月にはオセアニア事業の一部(飲料部事業)に続き、2022年にはミャンマー事業を売却してしまいましたが、飲料・酒類の国内市場の成長が期待できない現状では、事業構造改革の実行と新たな価値創造とともに、海外展開は避けては通れないパスです。
新たに入社する人材には、海外市場展開に対する期待も非常に大きいのです。
中期経営計画
キリンは2019年度に、2027年に向けた新たなキリングループ長期経営構想である「キリングループ・ビジョン2027」(略称:KV2027)を策定・発表し、KV2027の実現に向けた最初の3カ年計画として「キリングループ2019年-2021年中期経営計画」(略称:2019年中計)を基に事業を展開してきました。
既存事業領域である「食領域」(酒類・飲料事業)と「医領域」(医薬事業)に加え、キリングループならではの強みを生かした「ヘルスサイエンス領域」を立ち上げ、創業以来の基幹技術である発酵・バイオ技術に磨きをかけ、次世代の事業を育成してきました。
ヘルスサイエンス領域では、健康に寄与するエビフェンスを持つ素材の研究によってすでに、「プラズマ乳酸菌」による製品展開、普及促進に注力しています。また新たにグループに加えたファンケルとのシナジーも重視していく戦略です。
現在は2027年までの長期経営構想の第2ステージとなる「キリングループ2022年-2024年中期経営計画」(略称:2022年中計)を実行中です。
第2ステージでは、変革の基盤づくりを行った2019年中計から新たな成長軌道へシフトし、KV2027実現に向けた成長ストーリーを固めていくステージという期間性格となっています。
2021年度までに実現した成果を基礎とし、ポストコロナを見据えた事業構造改革の実行と新たな価値創造により、成長を加速することを基本方針として重点課題に取り組む計画です。
キリングループ2022年-2024年中期経営計画の重点課題:
- キャッシュ創出をリードする食領域での利益の増大
- 将来の大きな柱となるヘルスサイエンス領域での規模の拡大
- グローバル・スペシャリティファーマの地位を確立する医領域でのグローバル基盤の強化
食、ヘルスサイエンス、医の3領域の成長により企業価値を向上させるべく、ポートフォリオマネジメントを強化し、投資の優先順位を明確にすることで経営資源を集中していくことが大きな方針となっています。
中長期の大きな方向性としては、「酒類メーカーとしての責任」を果たすことを前提に、「健康」、「コミュニティ」、「環境」の4つの領域の課題解決を目指す内容となっています。
KV2027 は長期経営構想であり、また中期経営計画はその実現のための戦略としてこれからのキリンの方向性が分かるので、キリンを志望する方は必ず読んで頭に入れておきましょう。
アサヒグループホールディングス株式会社
2022年12月期連結決算(2022年度)
| 売上収益 (百万円) | 2,511,108 |
| 税引前利益 (百万円) | 205,992 |
| 当期利益 (百万円) | 151,717 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) | 151,555 |
| 当期包括利益(百万円) | 361,781 |
| 従業員数(人) | 29,920 |
| 外、平均臨時雇用者数 | 6,645 |
| 連結子会社 | 208社 |
| 関連会社 | 25社 |
アサヒグループホールディングスの事業セグメントの概要
アサヒグループは、持株会社であるアサヒグループホールディングスと連結子会社208社及び関連会社25社により構成される巨大企業です。
アサヒグループホールディングスは、グループ全体の戦略策定及び経営管理に特化するGlobal Headquartersと、各地域の特性に合わせた酒類 、飲料製品等の製造・販売の戦略を 策定・実行する地域統括会社であるRegional Headquarters(RHQ)から構成される経営体制を基にした事業セグメントに変更しています。
各RHQを管掌する責任者を配置し、グローバル戦略を踏まえた各地域における事業戦略の策定等を統括する体制とし、酒類、飲料製品等の製造・販売を基礎としたRHQの所在地域別のセグメント構成となっています。
具体的には「日本」、「欧州」、「オセアニア」、「東南アジア」の4つの事業を報告セグメントとして、以下の製品およびサービスを提供しています。
| 報告セグメント | 主な製品及びサービス |
| 日本 | 酒類、飲料、食品、薬品の製造・販売 |
| 欧州 | 酒類の製造・販売 |
| オセアニア | 酒類・飲料の製造・販売 |
| 東南アジア | 飲料の製造・販売 |
酒類の主要製品及びサービス
メインになる酒類事業はアサヒビール、ニッカウヰスキー、エノテカをはじめ、海外の有力連結子会社によって行われています。
アサヒの酒類事業はビール事業、中でもスーパードライが代名詞ですが、スーパードライのブランド拡張(生ジョッキ缶等)や、国内ではアサヒ生ビール(復刻版)も定番としてブランド確立、新ジャンルのアサヒ・ザ・リッチのマーケティングにも注力しています。
飲料・食品の主要製品及びサービス:
飲料事業はアサヒ飲料、カルピス、アサヒ飲料販売、食品事業はアサヒグループ食品という連結子会社を中心に、べビーフード・菓子・フリーズドライ食品・サプリメントなどの製造・販売行っています。
清涼飲料水はカルピスや三ツ矢サイダー等の定番ブランド、食品事業ではミント菓子のミンティアなど競争の激しいコンビニで棚を確保している商品の多く、飲料メーカーの中では最も元気でアグレッシブ、営業力が強いことが特徴です。
海外は北米、中国、東南アジア、欧州、オセアニアに連結子会社や合弁による連結子会社を設立して酒類事業を中心に展開しています。Asahi Beer U.S.A., Inc.が北米にてビールの販売、関連会社である 深圳青島啤酒朝日有限公司は中国にてビールの製造・販売をはじめとする等、世界各地の海外連結子会社によって事業を展開しています。
その他の事業は物流や本社機能、製造設備の設計や製作、情報処理などの事業によって構成されています。
[/box]2022年12月期(2022年度)連結業績の概要
2022年12月期における、アサヒグループホールディングスの連結業績は、売上収益が前期比12.3%増、2,750億3千2百万円増収の2兆5,111億8百万円となっています。
利益面では、事業利益*は2,438億1千7百万円(前期比11.9%増)、営業利益は2,170億4千8百万円(前期比2.4%増)、税引前利益は2,059億9千2百万円(前期比3.1%増)、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,515億5千5百万円(前期比1.3%減)という結果でした。
尚、親会社の所有者に帰属する当期利益から事業ポートフォリオ再構築及び減損損失など一時的な特殊要因を控除した調整後親会社の所有者に帰属する当期利益は、1,654億3千万円(前期比7.0%増)でした。
*事業利益は、売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除した、アサヒグループ独自の利益指標
連結収益は前年度に続いてコロナ前のレベル(2018年及び2019年12月期の業績)を超え、利益に関してもコロナ前の水準まで回復した決算となっています。
2022年12月期の事業セグメント別の業績概要は以下の通りです。
2022年12月期 セグメント別業績概要
| 事業名 | 外部売上収益(百万円) | 売上構成比 | セグメント利益 (百万円) |
利益構成比 |
| 日本 | 1,297,197 | 51.7% | 96,417 | 41.3% |
| 欧州 | 572,662 | 22.8% | 55,163 | 23.6% |
| オセアニア | 580,845 | 23.1% | 80,177 | 34.3% |
| 東南アジア | 51,639 | 2.1% | 633 | 0.3% |
| その他 | 8,764 | 0.3% | 1,257 | 0.5% |
| 合計 | 2,511,108 | 100.0% | 233,647 | 100.0% |
| 調整額 | ー | ー | -16,599 | ー |
| 計上額 | 2,511,108 | ー | 217,048 | ー |
日本:
- 売上収益はビールの売上が増加した酒類事業を中心に各事業が増収となり、前期比6.8%増の1兆3,017億3千1百万円
- 事業利益は、前期比5.3%増の1,089億1千3百万円(営業利益は前期比19.4%減の964億1千7百万円)
- 原材料関連やブランド投資の強化に伴う費用増加などの影響はあったものの、増収効果や各種コストの効率化が寄与
欧州:
- 売上収益が前期比21.0%増の5,738億7千5百万円
- 各国における飲食店向けの需要回復に加えて、グローバルブランドやノンアルコールビールの売上拡大や価格改定の効果が寄与
- 事業利益は、前期比0.7%増の760億5百万円 (営業利益は前期比19.8%増の551億6千3百万円)
- 主に原材料やユーティリティなどの費用増加の影響があったものの、飲食店向けの需要回復に加え、ブランドポートフォリオのプレミアム化の進展などに伴う増収効果や為替変動の影響が寄与。なお、為替変動による影響を除くと、売上収益は前期比13.5%の増収、事業利益は前期比6.3%の減益
オセアニア:
- 売上収益が前期比16.6%増の5,831億6千7百万円
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響はあったものの、ビールや炭酸飲料、スポーツ飲料を中心とした主力カテゴリーの売上拡大や為替変動の影響が寄与
- 事業利益は、前期比29.0%増の1,070億9千5百万円 (営業利益は前期比28.2%増の801億7千7百万円)
- 原材料関連の費用増加の影響などはあったものの、統合シナジーの創出を中心としたコスト効率化や為替変動の影響が寄与。なお、為替変動による影響を除くと、売上収益は前期比5.6%の増収、事業利益は前期比16.7%の増益
東南アジア:
- 売上収益は前期比21.1%増の516億8千万円
- 一部の国において新型コロナウイルスの影響が継続したものの、マレーシアにおける主力ブランドの販売が好調に推移したことに加え、マレーシア以外の展開国における新商品効果、価格改定や為替変動の影響などが寄与
- 事業利益は、前期比39.9%増の5億7千2百万円 (営業利益は前期比11億1千9百万円改善の6億3千3百万円)
- 原材料関連の費用や輸送費の増加などの影響があったものの、固定費全般の効率化などを推進したことが寄与。なお、為替変動による影響を除くと、売上収益は前期比6.8%の増収、事業利益は前期比27.6%の増益
その他:
- 売上収益は前期比47.0%増の87億6千4百万円
- 事業利益は、前期比13.4%増の14億7百万円 (営業利益は前期比45.5%減の12億5千7百万円)
アサヒグループホールディングスの事業計画
アサヒグループでは2019年より、グループ理念「Asahi Group Philosophy(AGP)」を制定し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して事業を展開しています。
AGPは、Mission、Vision、Values、Principlesで構成され、グループの使命やありたい姿に加え、受け継がれてきた大切にする価値観とステークホルダーに対する行動指針・約束によって構成されています。
Mission(社会的な使命・存在価値)は、「期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造」を掲げ、Visonでは「高付加価値ブランドを核として成長する“グローカルな価値創造企業”を目指す」としています。
そのための価値観(Our Values)は、「挑戦と確信、 最高の品質、 感動の共有」と定義しています。
アサヒグループ各社への就活を行う皆さんは、ぜひグループ全体を流れる共通のDNAを自分に当てはめて深堀して、自分事化してみて下さい。
また、AGPの実践に向けて、これまでの中期経営方針を長期戦略を含む新たな『中長期経営方針』として更新しています。
『中長期経営方針』では、長期戦略のコンセプトとして「おいしさと楽しさで“変化するWell-being”に応え、持続可能な社会の実現に貢献する」ことを掲げています。
主力の酒類事業では、ビールカテゴリーを中心として、プレミアム戦略の推進とグローバルブランドの拡大を上げています。
低アルコール飲料やノンアルコールビールテイスト飲料、成人向け清涼飲料などビール隣接カテゴリーを指す、BAC(Beer Adjacent Categories)に注力するなど、多様性や健康志向のニーズに応える付加価値提案も行っていく方針です。
また持続的成長を実現するためのコア戦略として、以下の3つの柱を立てています。
- サステナビリティと経営の統合による社会・事業のプラスインパクトの創出、社会課題解決
- DX=BXと捉え、3つの領域(プロセス、組織、ビジネスモデル)でのイノベーションを推進
- R&D(研究開発)機能の強化による既存商品価値の向上・新たな商材や市場の創造
尚、就活という側面では、アサヒビール、アサヒ飲料と酒類と飲料を分けて採用活動を行っているため、飲料に対する興味や価値観を絞って志望できるのもアサヒグループの特徴です。
是非チャレンジしてみて下さい。
サッポロホールディングス株式会社
2022年12月期連結決算(2022年度)
| 売上収益 (百万円) | 478,422 |
| 税引前利益/税引前損失 (百万円) | 11,367 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益/当期純損失(百万円) | 5,450 |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益(百万円) | 6,969 |
| 従業員数(人) | 6,676 |
| 外、平均臨時雇用者数 | 3,554 |
| 連結子会社 | 49社 |
| 関連会社 | 9社 |
サッポロホールディングスの事業セグメントの概要
サッポロホールディングスの事業セグメントはシンプルで、「酒類事業」、「食品飲料事業」、「不動産事業」、「その他事業」の4事業で構成されています。
各セグメントは以下の事業を行っています。
- 酒類事業:
- 酒類の製造(ビール、発泡酒、ワイン)・販売、各種業態の飲食店の経営等、ベトナム、アメリカ、カナダにおけるビールの製造販売
- 食品飲料事業:
- 食品・飲料水の製造・販売等、シンガポール、マレーシアにおける飲料水の製造販売
- 不動産事業:
- 不動産賃貸等、オフィス、住宅、商業、飲食、文化施設等の複合施設、及び商業、アミューズメント等の複合施設の管理・運営、グループの不動産事業の統括
- その他事業:保険の代理販売や関係会社への間接業務サービス
2022年12月期(2022年度)連結業績の概要
2022年12月期(2022年度)におけるサッポロホールディングスの連結業績の概要は以下の通りです。
- 売上収益:
- 全体では前期比9.4%増、413億円増収の4,784億円
- 売上収益は、食品飲料事業及び不動産事業が減収となった一方で、外食需要の回復やアメリカの売上数量が好調に推移したことで酒類事業の増収が寄与
- 事業利益:
- 全体では前期比14.4%増、12億円増益の93億円と
- 事業利益は、不動産事業が減益となった一方で、構造改革効果が寄与した外食事業や食品飲料事業の増益が寄与
- 営業利益:
- 119億円減益の101億円
- 営業利益は、事業利益が改善した一方で、前年の投資不動産の売却益の反動等が影響
- 親会社の所有者に帰属する当期利益:
- 親会社の所有者に帰属する当期利益は、営業利益の減益等により、前期比69億円減益の54億円
2022年度の事業セグメント別業績概要は以下の通りです。
2022年12月期 セグメント別業績概要
| 事業名 | 外部収益(百万円) | 売上構成比 | 営業利益/営業損失 (百万円) |
利益構成比 |
| 酒類 | 334,644 | 69.9% | 8,908 | 53.5% |
| 食品飲料 | 122,914 | 25.7% | 2,270 | 13.6% |
| 不動産 | 20,724 | 4.3% | 5,442 | 32.7% |
| その他 | 140 | 0.0% | 18 | 0.1% |
| 合計 | 478,422 | 100.0% | 16,638 | 100.0% |
| 調整・消去等 | ー | ー | -6,531 | ー |
| 計上額 | 478,422 | ー | 10,106 | ー |
サッポログループホールディングスの事業の特徴
サッポロの特徴は国内市場を中心として事業を展開している点です。外食産業は国内の飲食店を自ら経営している売上であり、不動産事業も自ら開発・所有している国内の不動産売上となります。
海外の中で最も売上シェアの高い北米の売上でも約17%であり、明らかに国内市場を重視した事業展開となっています。
海外酒類は2022年8月末に子会社化したSTONE BREWING CO.,LLCとのシナジー創出により成長を加速し、海外飲料はシンガポールを起点にマレーシア、中東等での売上拡大を目指していますが、業績への貢献はこれからの状況です。
また売上が少ないにもかかわらず収益に貢献しているのが不動産事業です。
主たる事業である酒類事業の2022年12月期の年度事業利益が77億円に対し不動産事業は65億円でした。
不動産事業は、ここ数年、主たる事業以上の数倍の利益をあげてきました。これは不動産事業の好調を意味するのではなく、本業の利益の少なさを物語っています。
サッポロを特徴付けるのは、売上の3割弱を占める食品・飲料事業です。2011年にポッカコーポレーションを買収しており、期間商品のポッカレモンやキレートレモンやインスタントスープ事業を展開しています。
サッポロに求められているのは、かつて市場に先駆けて第三のビール「ドラフトワン」をローンチして大ヒットさせたイノベーションや、その新ジャンルに味の良さを常識化した「麦とホップ」を開発したようなイノベーションです。
上位3社との競合が激しく簡単ではありませんが、黒ラベルやエビスビールなど、クオリティの意味で根強いファンももっているブランドの為、国内酒類事業の反転攻勢を期待するところです。
サッポロは、創業150周年となる2026年をゴールとした長期経営ビジョンSPEED150の具現化に向け、そのロードマップの一部となる中期経営計画「グループ経営計画2024」に取り組んできました。
2026グループビジョン:
「サッポログループは世界に広がる『酒』『食』『飲』で個性かがやくブランドカンパニーを目指します」
行動指針:
- イノベーションと品質の追求による新たな価値の創造で、世界のお客様のより豊かな生活に貢献します
- お客様同士のコミュニケーション活性化に役立つ商品・サービスの提供とブランド育成に努めます
- 環境変化に対応し、効率的な経営の実践に努めます
現在は、150年を越えて独自の存在価値を発揮し続けるために、2023年~2026年までの新たな4か年の経営計画を2022年11月に発表し、事業を展開しています。
新しい計画は「Beyond150 ~事業構造を転換し新たな成長へ~」を基本方針とし、そのポイントは、事業ポートフォリオの見直しと、各事業のポジショニングに沿ったグループマネジメントを実現し、資本効率を高め企業価値を向上させることを目指しています。
計画の概要は以下のとおりです。
中期経営計画(2023~26)の概要:
- 構造改革:
- 不確実性の高い環境に適応するべく、各事業を市場環境、独自の強み、サステナビリティ、収益性、シナジー、リソース配分の6つの視点から考察し、事業ポートフォリオの整理を行い、事業整理に位置付けた事業は速やかに整理を進め、再編に位置づけた事業は抜本的な見直し等、構造改革を断行する
- 強化・成長:
- 海外酒類は2022年8月末に子会社化したSTONE BREWING CO.,LLCとのシナジー創出により成長を加速し、海外飲料はシンガポールを起点にマレーシア、中東等での売上拡大を目指す
- 国内酒類は缶ビール、RTDの更なる強化により低収益から構造転換し成長軌道に乗せる
- 不動産は長期的な時間軸で賃貸中心から総合的に資産価値向上を図る事業体に転換し、収益性と資産効率の向上を目指す
上記の他、財務目標と非財務目標(CO2削減関連、女性役員比率)が設定されています。
上記は中長期計画の骨子の一部に過ぎません。
就活でサッポログループの企業を志望する方は、グループの課題や成長戦略をまで踏み込んで企業研究を行い、自分自身のビジョンと重ね合わせて語れるようにしておきましょう。
参考:コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスと日本コカ・コーラ

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスグループは、コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社をはじめとする子会社社9社、関連会社1社により構成されており、清涼飲料事業を主たる業務として行っています。
アメリカ合衆国ジョージア州アトランタが本社の ザ コカ・コーラカンパニーは飲料(含む原液)の販売を行う関係会社、日本コカ・コーラ株式会社はコカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社の発行済株式の15.59%を所有する筆頭株主という関係です。
飲料事業として、コカ・コーラ等の飲料の製造・販売を地域毎のボトラー各社が行う構造です。
傘下には自動販売機関連事業の子会社や不動産、保険代理、原料資材の調達、情報システムの構築を担当する子会社を持っています。
飲料事業:コカ・コーラ等の飲料の製造・販売:
- 飲料の販売:
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパンベンディング株式会社、FVジャパン株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパンビジネスサービス株式会社等
- 飲料の製造:
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
- 自動販売機関連事業:
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社等。
- 原材料・資材の調達:
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
- 情報システムの開発・保守運用:
- コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社
尚、ヘルスケア・スキンケア事業を行っていたキューサイ(青汁やコラリッチの製造・通販)もコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの連結子会社でしたが、2020年12月にキューサイの全株式をアドバンテッジパートナーズ、ユーグレナ、東京センチュリー3社に売却しています。
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
2022年12月期連結決算(2022年度)
| 売上収益 (百万円) | 807,430 |
| 税引前利益/損失(百万円) | -12,491 |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益/当期損失(百万円) | -8,070 |
| 親会社の所有者に帰属する当期包括利益(百万円) | -5,005 |
| 従業員数(人) | 14,484 |
| 外、平均臨時雇用者数 | 3,416 |
| 連結子会社 | 9社 |
| 関連会社 | 1社 |
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスは、2022年度の決算では売上高8,073.3億円を誇る立派な東証プライム上場企業です。
2022年12月期における、コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスの連結業績の概要は以下の通りです。
- 売上収益:
- 連結売上収益は、807,430百万円(前期比21,594百万円、2.7%増)
- 価格改定による販売数量へのマイナス影響があったものの、人出回復や猛暑による需要増加の機会を捉えるべく、新製品の展開や多様化する消費者ニーズに応じたチャネルごとの取り組みを実施したことにより、販売数量は前期比3%の増加
- 収益性の高いベンディングチャネルの数量成長や価格改定の実施によるケース当たり納価の改善が、売上収益の増加に貢献
- 第4四半期(2022年10月1日から2022年12月31日まで)には、10月に実施した小型パッケージの価格改定により、ケース当たり納価は全チャネルで成長
- 連結事業利益:
- 連結事業利益は、14,443百万円の損失(前期は14,662百万円の損失)となり、前期比増加(損失が減少)
- 数量成長や価格改定によるケース当たり納価改善の効果に加え、製造・物流効率の向上や変革の推進などによるコスト減少など、コントロール可能な分野においては約200億円の利益改善を実現したものの、原材料・資材・エネルギー価格高騰や円安などの外部要因によるコスト増加が大きく影響
- 連結営業利益:
- 連結営業利益は、11,513百万円の損失(前期は20,971百万円の損失から改善)
- 事業利益が前期比増加(損失が減少)したことに加え、有形固定資産売却益の増加や一時帰休に伴う休業手当費用(以下、一時帰休費用)の減少が貢献
- 親会社の所有者に帰属する当期利益:
- 親会社の所有者に帰属する当期利益は、8,070百万円の損失(前期は2,503百万円の損失から損失拡大)
- 営業利益が前期比増加(損失が減少)した一方で、前期に子会社であったキューサイ株式会社の株式譲渡による売却益を非継続事業において計上していたことによる反動などが影響
コカ・コーラボトラーズジャパンでは2019年8月に発表した中期計画の「これまでのやり方は選択肢にない」という方針を掲げ、主力の飲料事業に注力し、重要なベンディングチャネルや間接部門のコスト構造の見直し、製造能力の向上、新しい働き方の推進など重要施策によってビジネスの抜本的な変革を推進してきました。
現状は新型コロナウイルス感染症による行動制限が解除され、飲料需要は回復期にありますが、原材料やエネルギーコストの高騰、為替(円安)の影響が大きく、難しい状況が継続しています。
今後も、経済活動の活性化が飲料需要の増加に貢献すると予想されるものの、国内インフレの影響継続による消費者マインドの低下や飲料の価格改定(値上げ)などが市場動向に影響を及ぼすものと考えられます。
数量面では、価格改定によるマイナス影響を見込むものの、コアカテゴリーにフォーカスした戦略の実行や、イノベーションに基づく製品ポートフォリオの拡大、効果・効率を重視したマーケティング投資の実行などを遂行中です。
主な具体的取り組み:
- チャネル対策:
- ベンディングチャネルでは、投資効率を重視した自動販売機の新規設置活動
- スマホアプリ「Coke ON」等のデジタルプラットフォームの活用
- 手売りチャネルでは、新製品の積極的な展開や売場の拡大、適切な価格戦略およびマーケティング戦略の実行、カスタマーエンゲージメントの強化
- 日本コカ・コーラ株式会社との連携強化
- 製造・物流対策:
- 高品質・低コスト・安定供給を実現するサプライチェーンネットワークの構築
- 2022年に刷新したS&OPプロセス*の安定的な運用に注力するとともに、営業 (企画・販売)領域とサプライチェーン領域の連携をさらに深化
- 環境の変化に合わせた製品のタイムリーかつ低コストでの供給を実現
- 製造面では、海老名工場の新製造ライン稼働による製造キャパシティ向上や製造工程における効率化の推進、柔軟な製造体制の構築等
- 物流面では、2022年に立ち上げた「明石メガDC」の安定稼働や、営業・物流拠点の統廃合、製品在庫の低減・最適配置等により物流ネットワークの最適化を図る
- *S&OPプロセス(Sales and Operations Planning:販売・生産・調達までの一連の意思決定を早め、サプライチェーン全体の最適化を行う手法のこと)
コカ・コーラの飲料の開発とマーケティング全般は日本コカ・コーラ株式会社が専門で担当しているため、飲料マーケティングを志向する学生であれば、非常に難易度は上がりますが日本コカ・コーラを志望してみる価値はあります。
しかし、日本コカ・コーラは実力本位のキャリア採用が基本の外資系企業であることは覚悟してください。
そのマーケティングは非常に高度なレベルを要求しますので、業務はハードで、戦略コンサルのような働き方を求められると思った方が良いかと思います。
社内には海外でMBAを取得した人が多いのも特徴です。当然英語の能力はマストアイテムです。
日本コカ・コーラ出身で、外資系企業のマーケティングを渡り歩いて、ブランドマネージャーやディレクター、外資や日系企業の経営マネージメントに携わっている人も多く、プロ経営者への登竜門的な存在でもあります。
コカ・コーラボトラーズジャパンは製造と流通・販売のパートナーという位置づけになります。
まとめ
以上駆け足で業界の構造と飲料大手企業の概況を解説しました。大きなトレンドや企業の特徴、課題や今後の方向性は理解できたと思います。
飲料業界は競争が非常に厳しく、成長という視点では国内市場に期待できないため、マーケティングによるイノベーションで新たな市場を創っていくか、市場シェアを奪うか、海外に活路を求めるか、培ってきた技術背景を基にした新しい事業(食品・医薬品等)を創造・育成するしかしかありません。
このことを理解できれば、飲料大手が行っている事業戦略の目的や方向性が理解できると思います。
競争は厳しいですが、給与面や福利厚生、待遇は恵まれておりチャレンジ精神旺盛で、変化を受け入れ成長したいと思っている学生には「やりがい」のある業種であり、企業です。
志望してみたいと思った方は、ぜひ企業毎に深い研究を進めていってください。
この記事を読んだ人は、以下の記事も併せて読んでいます。
【平均は58点】あなたの就活力を診断してみよう
コロナ禍で学生生活を充実させることが難しかったことで、自分は就活をやり抜いて、納得の内定がとれるのか、不安を感じている就活生も多いのではないでしょうか?
そこで「就活力診断」で自分の実力をチェックし、すぐに動き出せるよう準備しておきましょう。
就活力診断を使えば、24の質問に答えるだけで、内定を勝ち取る実力があるかグラフで見える化してくれます。この診断ツールを使って、あなたの弱点を克服し、就活を成功させましょう。
またこのツールを利用する際、就活をより効率化できる無料の就活サービスを同時登録することも忘れずに!
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します