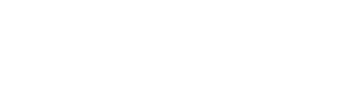就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。
「就活の答え」では鉄道業界を、以下の項目に沿って簡潔に情報をまとめていますので活用してください。鉄道業界情報の7つのポイントを押さえよう
- 鉄道会社のビジネスモデルを理解しよう
- 鉄道業界の現状と課題・未来
- 鉄道会社にはどんな仕事があるのか、職種の情報
- 鉄道会社に働く人のモチベ―ションは何か
- 鉄道会社に向く人、向かない人はどういう人か
- 鉄道業界の構造
- 主要鉄道会社の概況
Contents
鉄道業界の現状と課題
鉄道業は国土に鉄道を敷設し、鉄道を利用して移動する人や物の運賃で収益を得るビジネスです。自動車、航空機、船舶との違いは、走る車両、地上の線路、電気系統が一つのシステム構成し、且つ固定している点です。従って自社の路線上の人口や人口密度に大きく影響を受けます。
人口動態の変化

日本は既に人口減少社会に突入していることはご存知の通りです。日本が終戦を迎えた1945年時点の日本の総人口は7241万人でした。そこから高度経済成を遂げた日本の人口は2011年にピークの1億2770万人まで、ほぼ常に増え続けてきましたが2012年以降はついに減少トレンドに入っています。戦後から現在まで5000万人も増えた人口によって鉄道会社の成長が支えられてきました。
しかし総務省がまとめた「国土の長期展望」では、日本の総人口は、2050年には9,515万人となり、約3,300万人(約25.5%)減少することが予測されています。
高齢人口が約1,200万人増加するのに対し、生産年齢人口は約3,500万人、若年人口は約 900万人減少。その結果、高齢化率は約20%から約40%に上昇していきます。
この人口動態の変化は鉄道ビジネスに大きな影響を与えます。
鉄道は走る車両、地上の線路、電気系統が一つのシステムを構成して初めて機能する為、新しい路線をつくるには莫大なコストがかかってしまいます。人口減少が明らかな中で、新路線をつくる巨額の投資をして回収するのは不可能になりつつあります。
更に、生産年齢人口が減るということは、通勤人口(定期利用)の減少、ビジネスでの利用機会の減少を意味します。若年人口の減少は通学(定期)での鉄道利用も減っていきます。
その分高齢者は増加するので、高齢者がもっと鉄道を利用してくれれば良いのですが、体力の衰えと共に行動範囲が狭まって移動しなくなるのは避けられない事実です。
更に都市部への人口集中というトレンドもあります。地方や郊外は過疎化の問題に直面しています。
東京でも、かつては都心に通勤するサラリーマン家庭が、都下、千葉、埼玉、神奈川の郊外で、団地、マンション、一戸建てに居住して広がっていき、それによって鉄道利用者も増えていきましたが、現在では東京郊外でも高齢化は深刻になっています。
70年代、80年代には大学や高校なども都心から郊外へ移っていきましたが、近年は逆に都心の校舎へ戻るという現象も起きています。
地方では更に人口減少と高齢化が進んでおり、鉄道をはじめとしたインフラが支えられない地域も出てきました。
インバウンド需要の拡大

新型コロナウイルスのパンデミックによって状況は一変してしまいましたが、コロナ禍前の明るい話題は、訪日観光客の増加でした。2018年はついに年間3000万人の大台を超えました。政府はオリンピックがある2020年は更に1000万人増加して、4000万人を目標として、その達成は確実視されていたのです。
現状は全世界の国々へワクチン接種が広がり、人の移動の制限が緩和されて再び日本への観光が活性化することを待つしかありませんが、訪日外国人は観光やショッピングが主目的のため、鉄道を利用する機会の増加が期待できます。
日本の観光地を活性化して、インバウンド需要を更に拡大できれば、鉄道会社にとってもプラスの効果が期待できます。
航空会社やバス輸送との競争になりますが、鉄道網のポテンシャルを活かす方法は考えられるはずです。鉄道企業間の枠を超えた連携・提携など、課題を解決できれば成長は期待できます。
地方創生
日本政府は現状移民政策をとっていませんが、長期的には外国人労働者数は増えていくトレンドは変わらないでしょう。
政策面でもう一つ重要なのが、「地方創生」です。
現状は観光以外で目立った政策の成果が出ているとは思えませんが、地方で成長できる産業をつくり、過疎化を食い止めることができるかも一つの鍵になるでしょう。その際、鉄道会社も産業の創出や、地域経済の活性化の一翼を担うことになりますし、成功すれば鉄道や周辺ビジネスに対するプラス効果を期待できます。
現役就活生が2022年に鉄道会社に就職して、30年後の2052年の未来は決して楽観できないことは理解しておきましょう。
しかし民間企業である以上利益を出し、公共交通インフラを維持していくことは社会的な役割・責任も大きく、やりがいのあるビジネスであることは間違いありません。次は、鉄道会社が現状から未来に向けて行っている成長戦略の概要を把握していきましょう。
自分は鉄道業界に向いているタイプか、適性を診断してみよう
自分の適性や性格が、鉄道業界の仕事に向いているのかどうか、気になりませんか?
そんな時、力になるのは本格的な適職診断ソフト、「Analyze U+」です。
「Analyze U+」は251問の質問に答える本格的な診断テストで、質問に答えていくと経済産業省が作った「社会人基礎力」を基に、25項目に分けてあなたの強みを偏差値的に解析してくれるものです。
本当のあなたの強みや向いている仕事を素早く「見える化」してくれます。
「AnalyzeU+」を利用するには、スカウト型就活サイト「OfferBox![]() 」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
」への会員登録が必要です。もちろん全て無料で利用できます。
OfferBox![]() は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので登録して損はありません。
は、自分のプロフィールを登録しておくだけで、あなたに関心を持った企業から選考のオファーがもらえるサイトなので登録して損はありません。
手早く本格的で客観的な自己分析を済ませ、納得の結果を追求していきましょう。
鉄道会社の成長戦略

人口動態の変化は明らかでも、その問題がいきなり極端な影響を及ぼすことはありません。従って鉄道会社は時間を味方にすることはできるのです。
今までも沿線の大規模な不動産開発など、中長期のプロジェクトを手掛けるノウハウはあるので、適切な中長期戦略によって成長することは十分可能なのです。
身近な例ですが、東京都心部と近郊を結ぶJRや大手私鉄の路線で、利用者の多い通勤時間帯の急行や快速列車で1-2車両を特別仕様の指定席にしている例が増えています。普通車両は満員状態でも、指定席券を購入すれば余裕で通勤ができます。
普通電車が満員に近く、快適でない状況で、指定車両に空席が目立つ場合腹が立ったりすることもあるかもしれませんが、これも総需要が伸びない、もしくは微減していく中でいかに収益を稼ぐかという工夫の一つなのです。
通勤時間帯の郊外と都心を結ぶ移動客数が減少する際、1編成の車両数を減らしてもコストの削減がほとんどできないため、車両数をそのままにして収入を維持、もしくは増やす方法を考えた場合、客数の減少で生まれた空間にプレミアムをつけて販売することは合理性があるのです。
満席でなくともその時間帯にその列車を利用する客数は同じと考えれば、長期間で車両の改修コストを補えれば、あとはプラスになるという戦略なのです。これは人口減少や都心集中への対策の一つに過ぎませんが、この様な地道な工夫も大切なのです。
ターミナル駅の高機能化とブランディング

東急電鉄やJRが渋谷の再開発に注力しています。娯楽、飲食やショッピングだけではなく、ビジネスの中心街としての機能を着々と集積しています。それによって人の流れが渋谷に向かい、渋谷の価値が上がることは渋谷に乗り入れている東急沿線の価値も上がっていくという戦略です。
このような例は、JR東日本の東京駅、東京駅周辺の再開発、JR東海の名古屋駅の再開発、JR九州の博多駅周辺の再開発、西鉄の天神地区の再開発等数多く、今後も加速していくでしょう。山手線の新駅、高輪ゲートウェイもまさに沿線開発の事例です。
駅ビルの多機能化
メジャーな駅の付加価値を高めるのも一つの戦略です。
駅そのものや駅ビルのショッピングセンター化が進んでいますが、ホテル機能を付加したり、レジャー施設を付加したり、オフィス機能を付加するなど、駅の多機能化をさらに高度に進める戦略もあります。
駅直結のビルにオフィスやレジャー施設があれば、とても便利であることは明白です。郊外においてはクリニックや公共機関を集積してコンパクトシティの核にして、ワンストップで様々なサービスを受けられる便利な機能も付加できるでしょう。
このように駅及び周辺の資産を新しい価値を産み出すものに変えていくことで、輸送機能との相乗効果も狙う戦略です。
沿線住民へのサービスの事業化

大手、準大手の私鉄は沿線にスーパーマーケットを展開するなど、沿線住民の生活の利便性向上をひとつのビジネスチャンスとして事業を展開しています。またケーブルテレビなどの情報・通信インフラも事業化してきました。
その流れを更に発展させているのが、東京の京王電鉄の例です。京王は2007年から「京王ほっとネットワーク」事業を開始し、京王ストアの商品の宅配サービスから始まり、リフォームサービス、家事代行サービス、買い物代行サービス、ホームセキュリティサービスなど多彩な生活サービスを展開しています。これは沿線住民の高齢化や、共働世帯の増加に対応したサービスで、電鉄会社という安心感を事業に活かした価値創造であると言えます。
安心して生活できるインフラを提供すれば、京王線の魅力も高まり、子育て世代が好んで居住するなどの効果も期待できる訳です。
JRや東急が駅に保育所をつくっているのも同じ発想です。このように駅や不動産、安心感というブランディング利用した事業はまだまだ開発できる余地は十分にあるでしょう。
デジタル技術、IoTやAI技術開発と事業化

SuicaやPasmo、ICOCAなどの非接触型ICカードによって金融サービスを事業化した鉄道各社ですが、更にデジタル技術の応用によってビックデータの分析と活用、IoT技術やAI技術によって新しいサービスを産みだそうとしています。
一例ですが、JR東日本では2016年11月、「技術革新中長期ビジョン」を作成し、IoT、AI等によるモビリティ革命の実現に取り組んでいます。
コンセプトは、これまでの「駅から駅へダイヤ通りに輸送する」スタイルから「ドア・ツー・ドアでの移動と、需要に応じた臨機応変な列車運行」へと新たな移動サービスの創出を目指すというもので、例えば顧客が今いるところからアプリを起動して、行きたいところを入力すると、乗換案内はもとよりチケットの購入や、他交通機関とも連携も可能にすることで、鉄道だけでなくモビリティ需要のすべてをドア・ツー・ドアで賄える仕組みをイメージしているようです。
自動車メーカーも車を製造する企業ではなく、モビリティサービスを提供する企業とポジショニングをし直している時代なので、鉄道会社としても先端技術によって提供できるモビリティサービスを模索していくことは、今後とても重要になっていくでしょう。
海外事業
それほど例は多くありませんが、JR東海や東日本では車両メーカーと共に新幹線技術の輸出プロジェクトに参画したり、インフラとしての高速鉄道管理の海外展開、コンサルティング事業も手掛けています。また新幹線以外で海外事業を独自で事業化している例として東急電鉄をあげておきます。
東急は2000年代前半から参画していたオーストラリアの宅地開発事業(鉄道開通予定地)、ベトナムホーチミン市郊外での街区開発、タイでの日本人向け賃貸住宅事業など積極的に事業を展開してきました。
特にベトナム最大の都市ホーチミン市の北部約30kmに位置するビンズン新都市の開発では、日本国内における街づくりのノウハウを提供して街づくりのパッケージ輸出を行っています。鉄道会社にとって海外展開はハードルが高い事業ですが、東急のように実績を積み上げれば可能性は広がっていくでしょう。
まとめ
鉄道会社の現状と課題、そして未来への戦略を駆け足で解説してきました。就活の初期段階で、鉄道業界全般の課題や未来への戦略を理解するうえで重要な情報なので参考にして下さい。
鉄道業界を志望する場合、鉄道会社によって特徴も置かれている状況も大きく違うので、詳しくは1社ごとで詳細をみていく必要があります。
これから鉄道会社の総合職を目指す皆さんは、多角化による収益を出していくことはもちろんですが、どんどん新しいビジネス、事業を開発していく起業家マインドを持つことが非常に重要になっていくと思います。
人口動態の変化に起因する問題点は、チャンスでもあります。鉄道会社にしかできないことや、実現しやすいことは色々あるのです。
鉄道が好きなのは良いことですが、好きだけでは内定は獲得できません。+αの発想を常に持ってチャレンジしていきましょう。
この記事を読んだ人は、以下の記事も良く読んでいます。
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します