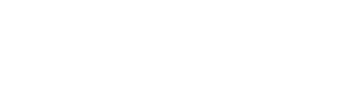就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。
「就活の答え」では小売業界を、以下の項目に沿って簡潔に情報をまとめていますので活用してください。
小売業界の7つのポイントを押さえよう
- 小売業界の業態を把握しておこう
- 小売業のビジネスモデルを理解しよう
- 小売業界の現状と課題・未来
- 小売業界にはどんな仕事があるのか、職種の情報
- 小売業界に働く人のモチベ―ション、「やりがい」は何か
- 小売業界に向く人、向かない人はどういう人か
- 主要小売各社の概況
Contents
小売業界の業態を把握しておこう

生活に密着している小売業なので、就活生の皆さんにも色んな業態の小売業、小売店がすぐ頭に浮かんでくるでしょう。またスーパーやコンビニでアルバイトをした経験のある方も多いと思います。そのため、就活に際して敢えて深く研究しなくても「単に商品を仕入れて売る業界」、「研究しなくても自分は分かっている」と思っていませんか?
実は小売業は皆さんが思っている以上に奥が深く、マーケティングという観点からも非常に面白い業界なのです。
また一言で「小売」といっても近所のコンビニからスーパーセンターと呼ばれる巨大店舗まで、あるいはリアルな店舗からECなど、実に様々な業態が存在しているため、細かく言えば業態ごとにビジネスモデルが存在します。
どんなお客様に対し、どういう価値を提供しているかが違うため、小売業を就活の対象として深く理解するにはその業態、その会社ごとの研究が必要になります。
この記事では、企業研究の前に小売業全体を俯瞰して理解することを目的にしています。まず、自分は「小売業界」に興味がもてるかどうかの材料にしてください。そのため、まず主要な業態を把握することからはじめましょう。
小売業の主要な業態
日本には様々な業態の小売業が存在していますが、就活の対象になる企業が行っている主要な業態をまず俯瞰しておきましょう。
スーパーマーケット:

売場面積の50%以上でセルフサービス方式を採用し、かつ、売場面積が1,500平方メートル以上の店舗がスーパーという業態です。食料品と日用品を中心に、日常生活のほぼすべてのニーズを満たす生活のためのインフラともいえる業態です。
食料品と日用品が中心の「食品スーパー」と呼ばれる業態と、衣料品や家電、小型家具などの衣食住のニーズを満たす「総合スーパー:GMS」に分けられます。
また、立地や住民のニーズによっては、輸入食品やワインなどを含む高級品の品揃えをしたスペシャルティ・マーケットや、逆に低価格を売りにしたディスカウント・スーパー業態など様々なバリエーションが存在しています。
コンビニエンスストア:
コンビニエンスストアは、高頻度で買われ、すぐに消費される加工食品、菓子類、飲料、総菜、酒類、たばこ、日用品、生活雑貨を中心とした品ぞろえと、宅配便やATMなど生活に必要な基本的なサービスの提供を行う業態です。
面積の狭い店舗で回転効率を追求した品揃えと24時間営業を基本として、直営店舗とフランチャイズ店舗を運用しています。また最近では立地、店舗によって一部生鮮食料品を置く店も増えてきています。
ドラッグストア:

ドラッグストアは薬品とトイレタリー商品、セルフ化粧品の販売に特化した業態として発達しましたが、近年では加工食品、飲料、酒類も販売するロードサイド店も増えています。
薬とセルフ化粧品、トイレタリー商品のディスカウント販売から、徐々にホームセンターや食品スーパーで販売されている消耗品や加工食品の領域を取り込んで事業を行っています。立地によっては外国人観光客向けに特化した店舗などの展開もおこなっています。
ホームセンター:
ホームセンターは食品以外の生活ニーズをすべて満たすワンストップ・ショッピング業態であり、ロードサイドに面積の広い店舗を展開しています。
品揃えはホームニーズ(インテリア、エクステリア、DIY、園芸関連、資材等)とハウスキーピングニーズ(日用品、生活雑貨、ペット関連等)が中心ですが、地方の大型店の場合建設資材や工具、農具、機械等を業務業者の業務用に販売することも行っています。
100円ショップ:
アメリカのワンコイン・ストアが源流ですが、日本ではワンコイン型バラエティストアとして独自の発展を遂げている業態です。
非常にキメの細かい、かゆいところに手が届く品揃えと税抜き100円商品という圧倒的な低価格で生活の基本的なニーズを満たしています。生活雑貨に加え、菓子、飲料、トイレタリー、化粧品なども取り込んでおり、一部、200円、300円、500円商品などの均一価格商品も展開しています。
ディスカウントストア:
販売する商品の全てを常に他のチェーンストアに比べて常時低価格で販売する業態です。
大量に販売に計画仕入れしたナショナルブランド商品・ストアブランド商品・プライベートブランド商品などを、計画数量を売り切ることや、在庫処分品などを仕入れることによって低価格を実現しています。
世界一の小売企業であるWal-Martもディスカウントストアから発展した企業です。日本では独自のコンセプトを開発したドン・キホーテやMr. Max、トライアル、ジェーソンなどが主にこの業態での事業を展開しています
専門店・スペシャルティ ストア:

衣料品、靴、クルマ用品、家電品等、領域を絞って展開する小売業です。ショッピングセンターに入っているテナントショップや、大型家電店など、扱っている商品も規模も大きく違います。
扱う商品の領域でディスカウント色を強く打ち出している大型家電店、家具店などは、カテゴリーキラーと呼ばれる場合があります。
SPA:
SPAとはspecialty store retailer of private label apparelの略で、ユニクロやしまむらなどの、自社独自の商品開発を行って自社の店舗のみで販売するアパレルの小売業のことを指しましたが、最近ではアパレル以外の家具や眼鏡、靴などの小売企業もこの方式を取り入れて事業展開を行っているため、SPA型企業という、ビジネスモデルとしての呼び方もされています。
その意味では無印良品、Zoff、JINS、ニトリなどもスペシャルティ ストアのSPA業態企業という位置づけになります。
スーパーセンター:

スーパーセンターとはWal-Martが開発、発展させた業態で、大型食品スーパーとディスカウントストア(日本のGMS、ホームセンター、家電量販店の扱う商品を常時低価格で販売)を一体化させて、生活に必要な衣食住に関わるすべての売り場を広大なワンフロアに集めて、一か所の集中レジで決済を行う業態です。
日本でもこの業態のコンセプトを見習い、日本流に一部アレンジして事業を展開している企業があります。ベイシアやプラント、イオンなどが主にこの業態を展開しています。
百貨店:
百貨店は経済産業省が実施する商業統計調査の基準によると、「衣・食・住の商品群の販売額がいずれも10%以上70%未満の範囲内にあると同時に、従業者が常時50人以上おり、かつ売り場面積の50%以上において対面販売を行う業態」としています。
また日本百貨店協会に加盟し、衣・食・住に関わる多種の品目を取り扱い、従業員による対面販売を主に行う商店で、売場面積が東京特別区及び政令指定都市で3,000平方メートル以上、その他の地域で1,500平方メートル以上の商店と定義されています。
百貨店には店舗における対面販売と外商があるのが他の小売業と違うところであり、高額、高級品を中心とした富裕層向け商品、ギフト・贈答、ビジネス需要、特別な機会での消費ニーズを満たしています。
ショッピングセンター:

日本ショッピングセンター協会によるショッピングセンターの定義はディベロッパーにより、「一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう」としており、更に以下の4条件を満たすものとしています。
- 小売業の店舗面積は、1,500㎡ 以上
- キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること。
- キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと。但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1,500㎡以上である場合には、この限りではない。
- テナント会(商店会)等があり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること。
ショッピングモールとも呼ばれ、食品スーパーやGMSのキーテナントの他に、専門店、ファッション・アパレルショップの他、グルメ・美容・アミューズメント・映画館・医療機関等の複合的な機能を備えた大規模展開が増えています。
ららぽーと、イオンモール等の全国展開ブランドや、地域限定の大規模モールが全国に点在しています。またアウトレットモールもブランドやメーカーの衣料品やアクセサリー等の処分品を集積した業態もシッピングモールの一とのカタチです。
ルミネやアトレ、ラフォーレなもショッピングセンターの一形態ですが、アパレルが中心の場合はファッションビルと呼ばれることも多いです。
その他の業態:
広い意味ではクルマのディーラーも小売業です。
また中古品販売業や、レンタルショップ、Eコマース(EC)事業者も含めると焦点が広がり過ぎてしまうため、これらの業態はこの記事では解説しません。
ただし、Eコマースに関してはリアルな小売業がEコマースを展開してたり、アマゾンや楽天をはじめとするEコマースが企業がリアルな小売業に与える影響に関しては別の記事で分析、解説していきます。
リアルな小売業の業態の概要を把握でできたら、小売業の基本のビジネスモデルを理解していきましょう。
まとめ
小売業の基本のモデルは商品を仕入れ、それを販売することにより、仕入れ価格と販売価格との価格差で、販売に関わる全ての費用をカバーした上で利益を得るというものです。
しかし、このモデルが基本ではあってもすべてではありません。それぞれの業態が理解できたら、現在の小売業の仕組みをビジネスモデルの視点からみていきましょう。
この記事を読んだ人は、以下の記事も併せて読んでいます。
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します