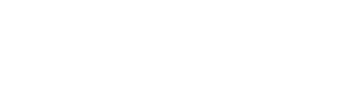活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。
「就活の答え」ではインターネット業界を、以下の項目に沿って簡潔に情報をまとめていますので活用してください。
インターネット業界情報の7つのポイントを押さえよう
- インターネット業界のビジネスモデルを理解しよう
- インターネット業界の現状と課題・未来
- インターネット業界にはどんな仕事があるのか、職種の情報
- インターネット業界に働く人のモチベ―ションは何か
- インターネット業界に向く人、向かない人はどういう人か
- インターネット業界の構造
- インターネット業界、主要各社の概況
Contents
インターネット業界を整理して考えてみよう
就活にあたって、IT業界やインターネット業界ほど捉えにくい業界はありません。IT(Information Technology) の意味、カバーする領域が広すぎて、IT業界と一言で言っても人によって想像する業界はバラバラでしょう。
この記事ではITと呼ばれる業界の内、インターネット業界、もっと正確に言えばインターネット情報サービス業界に特化して解説します。
ITと呼ばれる業界の中でも、コンピュータソフトウェアのSI業界、ハードメーカー(電機メーカー)、ゲーム業界、通信インフラ・サービス業界に関しては別の記事で詳しく解説しているので、そちらを参照してください。
インターネット情報サービス業界の定義と構造

この記事で扱うインターネット情報サービス業界とは、ざっくり総務省が「インターネット付帯サービス業」として分類している業界と理解して下さい。
総務省の分類では以下のビジネスをインターネット付帯サービス業として調査を行っています。
- ウェブ情報検索サービス
- インターネット・ショッピングサイト運営業
- インターネット・オークション・サイト運営業
- 電子掲示板・ブログサービス・SNS事業
- ウェブコンテンツ配信業 (5-1. うち、IPTVサービスによる収入)
- クラウドコンピューティングサービス(ソフトウェア開発を除く)
- 電子認証業
- 情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業
- 課金・決済代行業
- サーバ管理受託
- その他のインターネット付帯サービス
そもそもですが、インターネット情報サービスの仕事は一般的な企業の事業をインターネットという巨大インフラを通じて行っているという側面もあるのです。
現在ではほとんどのビジネスがEC機能を持つか、持たないかを問わず、インターネットなしでは成立しないことは誰しもが実感しているでしょう。
インターネット情報サービス業界は、企業や生活者のニーズやウォンツをインターネット、Webを媒介にして満たすために存在している事業と考えれば良いでしょう。
企業の提供するサービスもアメーバのようにビジネスの領域を取り込み、かつ変化させている業態であるため、「業界・業種」という枠組みで捉える「就活」ではまとめることが難しく、まとめて語れないというのが真実です。
従って、この領域の仕事に興味がある学生は、ざっくりインターネット業界を把握した後、ターゲット企業を決めて個別の企業研究を詳細に行った方が実践的であるとも言えます。
何故なら、総務省がカテゴライズした上記のビジネスも、多くのインターネット企業が複数の領域を手掛けているためです。また上記の領域をおこないつつ、ゲームを提供している企業も沢山あります。
リアルなビジネスや幅広い業界の事業をインターネットやIT技術を武器に参入している企業もあるため、企業という枠で業界、業種、業態を分類するのが難しいためです。
総務省の分類も統計データの必要性があるため、何らかの分類をしたものと考えた方が良いでしょう。この領域のビジネスは常に変化をして、捉えどころがないというのが実態に近いと理解しましょう。
インターネット情報サービスの捉え方
インターネット情報サービスのビジネスを、BtoB, BtoC, BtoBtoC, CtoCというように、誰に対し何の価値を提供しているのかを考えるのも、就活という文脈では有効です。
何故なら自分は何に喜びを感じるかと結びついているためです。以下にその定義を解説しておきます。
BtoBとは企業向けにサービスを提供するビジネスです。企業や官公庁の受託システム開発がその典型になります。
また企業向けクラウドサービスやWebサービスのユーザーインターフェイスに関するデザイン、コンサルティングやWebサイトの制作・運用代行等もBtoBビジネスです。
情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業、課金・決済代行業、電子認証作業、サーバ管理受託などもこの分類になりますが、個人相手のビジネス領域もあるため本当の意味での線引きはできません。
BtoCとは消費者向けにインターネット情報サービス業界を提供するビジネスです。
Google やYahooのような検索サービスや、ポータルサイトが提供するビジネス、SNSサイト、AmazonをはじめとするECサイトが含まれます。
ECサイトはメーカーやリアル小売業が運用しているものも多いため、ここではインターネット・Webサービス発のECサイトビジネスと考えてください。
BtoBtoCは、企業が個人消費者相手に商売するのを、手伝うビジネスです。
インターネット広告代理店や楽天のECビジネスを考えると分かり易いと思います。
インターネット広告代理店は広告業界に分類して扱われることが多いため非常に線引きが難しいテーマです。各種保険、旅行、引っ越しサービス、ふるさと納税、転職ポータルなど幅広いビジネスが存在しています。
CtoCは消費者同士がモノや情報のやりとりを行うのを手伝うビジネスと考えれば分かり易いと思います。メルカリやオークションサイトのビジネスを考えれば分かり易いでしょう。
インターネット・オークション・サイト運営業、電子掲示板・ブログサービス・SNS、CGMのウェブコンテンツ配信業などが含まれますが、BtoCでのビジネスも展開や広告メディアとしてはBtoBtoCのビジネスモデルにもなるため、切り分けられないというのが実情です。
更に、あるサービス単独では利益が出なくても、そのサービスに付随するもので収益化し、トータルの事業として成り立てば良いという割り切りや、リアルなビジネスをインターネットという巨大なメディアを使った新しい販売チャネルをつくるなど、多様な稼ぎ方を創造できる業界なのです。
収益化の代表的モデル

基本的に「なんでもあり」の業界ですが、就活生の皆さんが最も興味を持っているWebコンテンツ事業の代表的な収益モデルを解説します。
広告収益モデルは自社のWebサイトに広告枠や、広告機能を設けて広告主から広告費を得るモデルが基本になります。Webサイトがメディアとして情報を提供する、あるいはサービスを提供することで、そこにアクセスした人々に対する広告という価値を提供してマネタイズするモデルです。
コンテンツ課金モデル:
インターネットで有料コンテンツをみる、あるいは定額のサブスクリプションフィーを払えばコンテンツを見放題になったり、音楽を聴き放題にしてユーザーから収益を得るモデルです。
有料アプリやゲームでの課金モデルもコンテンツ課金モデルになります。アプリやソフトで無料で享受できる部分と、課金・有料でしか享受できないサービスやコンテンツを提供してマネタイズするモデルもこの範疇です。
仲介手数料モデル:
インターネット上にプラットフォームを提供し、企業と企業、企業と人、人と企業を結び付け、そこで行われるビジネス、取引、情報や関係構築などの成果に対し手数料を徴収するモデルです。
保険、旅行・宿泊、引っ越しなどの一括サービスやヤフオク、メルカリなどのビジネスを考えれば分かり易いでしょう。
インターネットを経由しての物販ECが代表的ですが、サービスの提供も含まれます。アマゾンや楽天をはじめレンタルサービスなどがあります。
物販の場合、自社で商品を仕入れて販売するモデルとショッピングモール型のサイトを運営して、そこに出店させ出店料としてマネタイズするモデルに分かれます。
実際には上記の4つの収益モデルの中でも細かく細分化されています。
例えば、広告収益モデルの中でも、インプレッション課金、クリック課金、コンバージョン課金など、多様なモデルが存在します。
大手インターネット情報サービス企業は上記の基本的なモデルを組み合わせて事業を行っているのが普通ですし、むしろ常に新たなサービスやマネタイズの方法を考え続けている業界と理解してください。
変化により成長するモデル

「変化の激しい時代」と言われて久しいですが、インターネット業界ほど変化の激しい業界は有りません。その意味でまさに時代をリードし、時代を代表する産業でもあります。
逆に言えば変化に対応できなければ、すぐにすたれてしまうリスクがあり、他社が優れたサービスで参入してくれば、あっという間にシェアを失ってしまう業界なのです。
かつて日本のSNSの代表的存在であったミクシィも、TwitterやFacebookにシェアを奪われSNS事業が下火になってしまいましたが、2013年に発売した「モンスターストライク」のヒットで復活しました。
しかしその後、モンストの大成功で収益がモンストに依存する構造になってしまいました。将来的にゲームが飽きられてしまうのは避けられないことであり、現在ではメディアプラットフォーム事業等、新たな事業の開発に注力しています。
企業の生き残りや成長のためには事業の中身を素早く変化させていく必要があるのがインターネット情報ビジネスのビジネスモデルです。従って定型のビジネスモデルはないと考えた方が良いのです。
就活のいう文脈の中では、インターネットに興味や魅力を感じることは当然として、「非常に速いスピードの中で、どんどん変化していくことを楽しめるか、そういう世界に魅力を感じるか、柔軟に対応できるか」という点が判断規準になる業界なのです。
この記事を読んだ人は、以下の記事も併せて読んでいます。
広告や、マーケティングに携わりたいという方は、「シンアド就活」を使ってみる手がある
事務系の総合職を希望するが、自分に営業職が務まるのかどうか不安な方や、営業職の中身を知りたい、営業以外の職種の可能性を知りたいと思っている就活生ならば、「シンアド就活」という就活サービスを利用してみる手があります。
「シンアド就活」は、広告・IT業界専門の就活情報サイトです。
有名企業からベンチャー・スタートアップ企業まで幅広い選択肢の中から、あなたの適性に合った企業を紹介してくれる就活サービスです。
もちろん、就活生は完全無料で利用可能。
就業経験のない就活生が、企業を見極めるのはとても難しいのが実態です。
「シンアド就活」では、業界に精通したアドバイザーがあなたの就活を二人三脚でサポートしてくれます。
もし、広告・IT業界に興味があるが、自分の適性が分からない、マーケティングに興味はあるが、自信がないとも持っている方は、まずは会員登録をして相談だけでもしてみませんか?
\\\ まずは、会員登録から ///
36の質問で、あなたの強み・適職を診断
 就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。
そんな時は、自己分析ツールを活用しましょう
キャリアパークのツールを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。
サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。
あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5
-
 1
1
-
26年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスで、インターン情報やスカウトをもらおう
資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、SoftBnak、JCB、ATEAM、sansan、Nissin、Opt、Funai Soken、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう
-
 2
2
-
25年・26年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある
少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生、インターンに参加したい26年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!
-
 3
3
-
納得できる内定獲得のための就活サイト、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!
就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう
-
 4
4
-
落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある
スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう
-
 5
5
-
【25年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう
もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します